事なかれ主義とは?意味、性格的特徴、心理的背景、会社への悪影響と改善策
 公開日:2025.10.09
公開日:2025.10.09
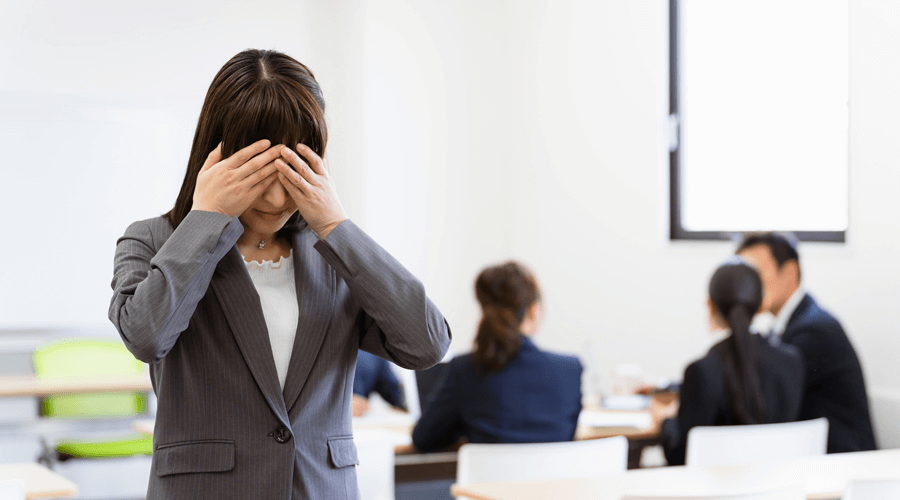
事なかれ主義とは、問題やトラブルが生じた際に、積極的な解決を避けて波風を立てずに済ませようとする考え方のことです。一見すると職場の調和を保つ配慮のように思えますが、実際には責任逃れや問題の先送りといった行動が会社全体に悪影響を与えるため、蔓延防止に向けた対策が必要です。
本コラムでは、事なかれ主義の意味や性格的特徴、心理的背景、会社に与えるリスクと効果的な改善策について詳しく解説します。
事なかれ主義とは
事なかれ主義について正しく理解するために、まずは基本的な意味とビジネスシーンでの具体例について見ていきましょう。
事なかれ主義の意味と語源
事なかれ主義とは、問題やトラブルに直面した際に、波風を立てずに穏便に済ませようとする考え方や態度のこと。語源的には、「事」(問題・トラブル)、「なかれ」(してはいけない・避けるべき)、「主義」(思想・方針)という3つの要素から構成される言葉です。
事なかれ主義という言葉が生まれたのは、記録によると日本の経済学者・和田垣謙三が大正2年(1913年)に発表した「兎糞録(とふんろく)」という作品で使用された例が確認されています。現在では企業や社員の思想・行動パターンを表す言葉として定着しています。
職場における事なかれ主義の具体例
事なかれ主義は、一般的に職場において以下のような行動、態度として現れます。
- 会議で改善提案など積極的な発言を控える
- トラブルが発生しても様子見の立場を取る
- 新たな挑戦より現状維持を選択することが多い
- 問題を見つけても直接指摘しない
表面的には「協調性がある人」という印象を与える場合もありますが、実際はその行動が組織の成長を妨げる原因となるため、改善・防止の対策が必要です。
事なかれ主義の類義語・対義語と関連表現
続いて、事なかれ主義の類義語と対義語、混同されやすい概念との違いを見ていきましょう。
事なかれ主義の類義語・言い換え表現
ビジネスシーンで「事なかれ主義」と近い意味で使われる表現には、以下のようなものがあります。
【事なかれ主義の主な類義語・言い換え表現】
| 表現 | 意味 |
|---|---|
| 当たらず障らず | 相手に迷惑をかけないよう注意深く行動し、差し障りのないように物事を進める態度。トラブルを避けて無難にその場をやり過ごそうとする姿勢を指す |
| 傍観 | 問題や出来事に対して、関与せずにただ見ているだけの態度。積極的な関わりを避け、第三者的な立場を維持しようとする |
| 保守的 | 従来の方法や慣習を重視し、変化を好まない姿勢。ただし、伝統や既存の価値を積極的に守ろうとする姿勢も含まれる点に注意 |
| 官僚主義 | 規則や手続きに過度に依存し、柔軟性を欠く組織運営のあり方。リスクを避けて既存のルールに従うことを優先する |
この中でも「当たらず障らず」は事なかれ主義に最も近い表現で、日常的なコミュニケーションにおいてよく使われます。
注意点として、「保守的」については必ずしも消極的とは限りません。「積極的に伝統を守る」という意味で使う場合もあります。
事なかれ主義の対義語
事なかれ主義とは対極にある「積極的な姿勢」を表す言葉には、以下のようなものがあります。
【事なかれ主義の主な対義語】
| 表現 | 意味 |
|---|---|
| 積極主義 | あらゆる物事に対して能動的に取り組み、自発的に行動しようとする考え方。問題回避ではなく、問題解決に向けて積極的に動く姿勢を指す |
| 進取果敢(しんしゅかかん) | 自ら積極的に行動し、困難な状況にも果敢に挑戦する。リスクを恐れず、決断力を持って前進する態度のことをいう |
| 事大主義 | 些細な物事を大げさに扱い、必要以上に騒ぎ立てる行動をとる。穏便に済ませようとする事なかれ主義とは対照的な考え方 |
「積極主義」は一般的な能動的姿勢を表すのに対し、「進取果敢」はより強い意志力と行動力を示します。
なお、「事大主義」は事なかれ主義とは真逆の行動パターンですが、過度に大げさに反応する点で、これもまた組織にとって問題となる傾向があります。
平和主義と事なかれ主義の違い
事なかれ主義は平和主義と混同されがちですが、両者には大きな違いがあります。
平和主義は、対立や争いを避けながらも、建設的な対話や協調を通じて積極的に平和を構築しようとする考え方です。問題に向き合い、解決策を模索する姿勢を持っています。
一方、事なかれ主義はこうした積極性がないため、建設的な平和主義とは性質が異なります。
事なかれ主義の心理的特徴
事なかれ主義に陥りやすい人には、次のような心理傾向や行動パターンが見られます。
責任回避と責任転嫁
事なかれ主義の人は、あらゆる場面で自分の発言や判断の責任から逃れようとする傾向が見られます。意見を求められても無難で曖昧な返答をし、他のメンバーと異なる考えを持っていても、多くの場合、自分の意見を主張したり反論したりしません。
特に、何か大きな問題が発生した際はこの傾向が顕著に現れます。「上司の指示が不明確だった」「他部署との連携不足のせい」と外的要因に責任を転嫁し、自分の関与を最小限に見せることもあります。
この責任転嫁の背景には、自信のなさや、職場で不利益を被ることへの過度な恐れが隠れていると考えられます。
向上心の欠如
さらに、事なかれ主義には向上心の欠如という特徴も挙げられます。新しいアイデアの提案や業務プロセスの見直しなど、創造性や積極性が求められる場面では特に消極的になる傾向が見られます。
これは、革新的な取り組みが失敗するリスクを恐れ、「何もしなければ責められることもない」という消極的な安全志向が働くことが影響しているのかもしれません。
安全志向・現状維持志向
事なかれ主義の人は、変化やリスクを嫌い、現在の安定した状況を維持することを優先しがちです。慣れ親しんだルーティン業務を「安全地帯(コンフォートゾーン)」として捉え、そこからなかなか出ようとしない人も少なくないでしょう。
例えば、新しいプロジェクトへの参加や役割の変更を提案されても、「リスクを冒してまで変える必要はない」と考え、現状維持を選択します。
この心理は人間の本能的な部分でもありますが、事なかれ主義の人は特にその傾向が強く、組織の成長や変革の妨げになりやすい点が問題とされています。
問題を先送りしがち
目の前に問題が発生した際、「誰かが何とかしてくれるはず」と他人任せにして自ら積極的に解決しようとしないのも特徴です。当事者意識が低く、その問題が自分や組織にどのような悪影響を与えるか想像できないのです。
特に、問題解決するために周囲と摩擦が生じたり、自分に何かしらの負担が伴ったりする場合、他の人に責任を押し付け、見て見ぬふりする行動が目立つようになります。
このような行動は小さな問題を大きなトラブルに発展させる原因となり、最終的には組織全体に深刻な損失をもたらすリスクを抱えています。
事なかれ主義に陥る2つの原因
事なかれ主義の発生原因は様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられますが、大きく分けると個人の内面に起因するものと、組織環境によって引き起こされるものの2つに分類できます。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
個人に起因する原因
事なかれ主義に陥る原因としてまず挙げられるのは、個人の性格や価値観、過去の経験に何らかの問題があるケースです。これには自己肯定感の低さが特に大きな要因となっており、「自分の意見なんて価値がない」という思い込みが積極的な行動を制限してしまいます。
また、失敗や批判に対する過度な恐怖心も影響していると考えられます。過去に意見を述べて批判された経験や、積極的に行動して失敗した記憶がトラウマとなり、「波風を立てないのが一番安全」という防御的な思考パターンを作り上げてしまうのです。
組織に起因する原因
一方で、個人的な問題がなくても、組織の環境や文化が事なかれ主義を助長してしまうケースも少なくありません。
組織の問題として最もよく見られるのが、「仕事の失敗は決して許されない」といった厳しすぎる組織風土です。ミスをしたことを必要以上に責められる環境では、社員は「失敗するくらいなら何もしない方がマシ」と考えるようになります。挑戦意欲が削がれると、さらに安全志向が強まるでしょう。
ほかにも、評価制度が適正に機能していないことが原因として挙げられます。頑張った人と手を抜いた人の処遇に差がつかないため、「努力しても無駄」という諦めの感情が広がるのです。加えて、上司からのフィードバックが不足している場合も、成果への手応えを感じられず、モチベーションの低下を招きます。
そして、既存のルールや慣習が絶対視されているような環境も要注意です。「昔からこうやってきた」という理由で新しい提案が却下され続けると、社員は意見を出すこと自体を諦めてしまいます。
事なかれ主義が会社に与えるリスク
事なかれ主義が会社に蔓延すると、個人レベルの問題に留まらず、チーム全体、さらには会社全体の成長や競争力に深刻な悪影響を与えます。ここでは、事なかれ主義が組織にもたらす具体的なリスクについて詳しく解説します。
組織のモチベーション低下と受け身体質の蔓延
事なかれ主義が職場に広がると、最も顕著に現れるのがチーム全体のモチベーション低下です。積極的に発言したり行動したりする社員が評価されず、むしろ「余計なことをする人」として敬遠される雰囲気が生まれ、他の社員も消極的になっていきます。
この状況が続くと、
- 上司からの明確な指示がない限り動かない
- 自分から提案や改善案を出さない
- 問題が発生しても「誰かが対処してくれる」と他人任せにする
といった事なかれ主義の典型的な行動パターンが常態化します。やがて業務効率が大幅に低下し、他部署との連携にも支障が出てくるでしょう。特定の積極的な社員に業務が集中し、チームや組織全体のバランスが崩れてしまいます。
イノベーションの停滞
事なかれ主義が蔓延した組織では、新しいアイデアや革新的な提案が生まれにくくなります。「反対意見を言われるかもしれない」「失敗したら責任を問われる」という不安から、皆が創造的な発想を封印してしまうからです。
現代のビジネス環境では、「市場の変化に迅速に対応すること」「新規事業の創出を続けること」が企業の生存に直結するといわれています。
しかし、事なかれ主義が支配的な組織ではイノベーションが停滞し、既存業務の維持で精一杯の状態が続くでしょう。
コンプライアンス違反や不正の温床に
事なかれ主義で最も懸念されるリスクとして、不正行為やコンプライアンス違反の常態化が挙げられます。
問題のある行為を目撃しても「面倒なことに巻き込まれたくない」という心理から、多くの社員が見て見ぬふりをします。こうした状況が続くと、組織内で「多少の不正は仕方ない」という空気が醸成され、次第に倫理観が麻痺していくのです。
小さな違反行為が徐々に拡大し、最終的には企業全体の信頼失墜や大規模な不祥事につながる危険性も考えられます。
特に大きな組織では、部門間での責任の押し付け合いや不正行為の正当化が起こりやすいため、組織全体のモラル低下という悪循環に陥りがちです。
優秀な人材の流出
事なかれ主義が支配的な職場では、意欲的で成長志向の強い社員ほど不満を感じやすく、優秀な人材から順番に転職を検討するようになります。
一方で、事なかれ主義の社員は変化を求めず現状維持を好むため、組織に残り続けます。この結果、組織全体のスキルレベルや活力が徐々に低下し、新しい課題に対処する能力が失われていくでしょう。
また、外部から優秀な人材を採用しても、既存の事なかれ主義の文化に阻まれて本来の力を発揮できず、早期離職につながるという負の連鎖が見込まれます。
事なかれ主義の社員を改善するための3つの方法
こうした最悪の事態を避けるには、事なかれ主義に陥った社員を早期に改善する必要があります。社員一人ひとりの背景にある原因を見極め、個別の対策を講じなくてはいけません。
ここでは、事なかれ主義の改善に効果的な方法を、原因別に3つご紹介します。
当事者意識を高めるアプローチ
「当事者意識の欠如」が原因として考えられる場合、社員が「自分事」として業務に取り組めるような環境づくりが有効です。
定期的に会議やミーティングの機会を設け、一対一の面談を行い社員の考えを聞き出しましょう。最初は簡単な質問から始めて、変化が見えてきたら深い意見を求めるなど、段階的に進めるのがポイントです。
また、社員一人ひとりに「仕事において期待していること」を具体的に伝えることも大切です。社員が自分の存在意義を実感できるようになれば、やがて何事にも積極的に関わろうとする気持ちが芽生えてくるでしょう。
責任感を育てる取り組み
責任感不足が原因の社員には、仕事内容の見直しとともに、徐々に責任のある業務を任せる取り組みが効果的です。
まず、現在取り組んでいる業務がなぜ重要なのか、会社や顧客にどのような影響を与えるのかを丁寧に説明します。業務の意義や価値を理解してもらうことで、真剣に取り組む気持ちが生まれやすくなります。そして、達成度を確認して、徐々に難易度の高い内容の仕事を任せていきましょう。
ただし、いきなり高いハードルを設定すると萎縮させてしまう危険性があるため、本人の能力を少し上回る程度に設定するのがポイントです。「この仕事は君にしかできない」といった言葉も伝えることで、責任感の向上と同時に仕事のやりがいも感じられるようになるでしょう。
向上心を刺激する環境づくり
向上心の欠如が見られる社員には、まず本人の自己肯定感を高めることから始めましょう。小さな課題から取り組ませ、達成できたら必ず褒めることで、「自分にもできる」という実感が生まれ、次第に難しい挑戦にも前向きになります。
評価を伝える際は、他の社員と比較するのではなく、その人自身の成長に焦点を当てましょう。自分なりのペースで成長していることを実感できれば、向上心も自然と湧いてきます。
研修やセミナー、eラーニングなどの学習機会を用意することも大切です。自主性を育てるため、課題を会社が一方的に決めるのではなく、本人の興味や将来の目標に合わせ、各自で自由に選べるようにしましょう。
事なかれ主義の蔓延を防ぐ取り組み例
事なかれ主義は一度根付いてしまうと改善に時間がかかるため、いかに予防できるかが重要です。定期的に組織風土や制度を見直し、事なかれ主義が生まれにくい環境をつくりましょう。
最後に、事なかれ主義防止のための具体的な取り組み例をご紹介します。
多様性を受け入れる組織文化の構築
異なる価値観や経験を持つ人材を積極的に受け入れることで、事なかれ主義を防ぐ土壌を作ることができます。多様性の推進は、固定観念を打破し、活発な議論が生まれる環境を整える重要な要素です。
人材の多様化を進める取り組みとして、以下のようなものが挙げられます。
【人材の多様性を進める取り組み例】
| 取り組み内容 | 期待される効果 |
|---|---|
| 中途採用の積極化 | 他社の成功事例や新しい手法を組織に持ち込むことができる |
| 部門間の人事異動 | 部署の垣根を越えた視点で多角的に問題を捉えやすくなる |
| 若手の積極登用 | 慣習にとらわれない新鮮なアイデアが生まれる |
| 外部人材の活用 | 専門家の視点から客観的な意見を得られる |
多様な背景を持つメンバーが混在することで、1つの問題に対して複数の角度からアプローチできます。その結果、問題や課題に正面から向き合う文化が醸成されていきます。
透明性の高い報告体制の整備
問題や不正をいち早く発見し、適切に対処できるような報告体制の整備が求められます。社員が安心して声を上げられる環境をつくりましょう。
【具体的な取り組み例】
- 気軽に相談できる匿名ホットラインの設置
- 人事部や外部機関など、複数の相談ルートの確保
- 報告内容を適切に管理し、対応状況を追跡できる記録・管理システムの導入
また、組織として内部告発をどのように扱うかを明確にし、全社員に周知していく取り組みも重要です。
【周知すべき内容】
- どのような内容を報告できるのか
- 匿名性はどの程度保護されるのか
- 報復措置は絶対に許さないという方針
挑戦を評価する人事制度の導入
「リスクを恐れて行動しない社員」よりも、「失敗を恐れず挑戦する社員」を評価する制度に変えることで、事なかれ主義を予防できます。
その鍵となるのが、減点主義から加点主義への転換です。ミスをしなかった人ではなく、新しいことに挑戦した人、改善提案を多く出した人、積極的に発言した人を高く評価するようにします。「結果が期待通りでなくても、その過程や学びを評価する」という企業理念を全員に浸透させることが大切です。
また、評価基準を明確にし、なぜその評価になったのかを本人に丁寧にフィードバックする仕組みづくりも同時に行いましょう。公正な評価制度は、社員のモチベーション向上にもつながります。
心理的安全性の向上
失敗や意見の違いを恐れずに発言できる環境を作ることも、重要な取り組みの1つです。
例えば、何かミスが発生したときは、犯人探しに焦点を当てるのではなく、「なぜそのようなことが起きたのか」「今後どう改善すればよいのか」に焦点を当て、建設的な議論を進めることが大切です。「失敗も学習の機会」と捉える組織文化が根付けば、社員は萎縮せず積極的に行動できるようになるでしょう。
日常的な取り組みとして、管理職が部下の前で自分の弱みや失敗談を語ったり、「わからないことがあれば何でも聞いて」と気遣いの言葉をかけたりすることで、相談しやすい雰囲気を作り出せます。
そして、定期的な1on1面談やメンター制度の導入も効果的です。上司と部下、先輩と後輩が腹を割って話せる機会を増やせば、日頃感じている小さな不安や悩みを互いに共有しやすくなります。
継続的な意識改革の取り組み
事なかれ主義の弊害について全社員が正しく理解できるように、研修やワークショップを実施し、意識改革に向けた取り組みを続けましょう。他社の成功事例や失敗事例を学ぶ機会も設け、改革の重要性を具体的に理解してもらうことが大切です。
これらの取り組みは一朝一夕で効果が現れるものではありませんが、継続的に実施することで必ず組織の風土は変わります。事なかれ主義が根付く前に、社内に生じた小さな異変も見逃さず、適切な予防策を講じていくことが重要です。

