ファイナンスとは?意味や会計・金融との違いなどを解説
 公開日:2025.09.05
公開日:2025.09.05
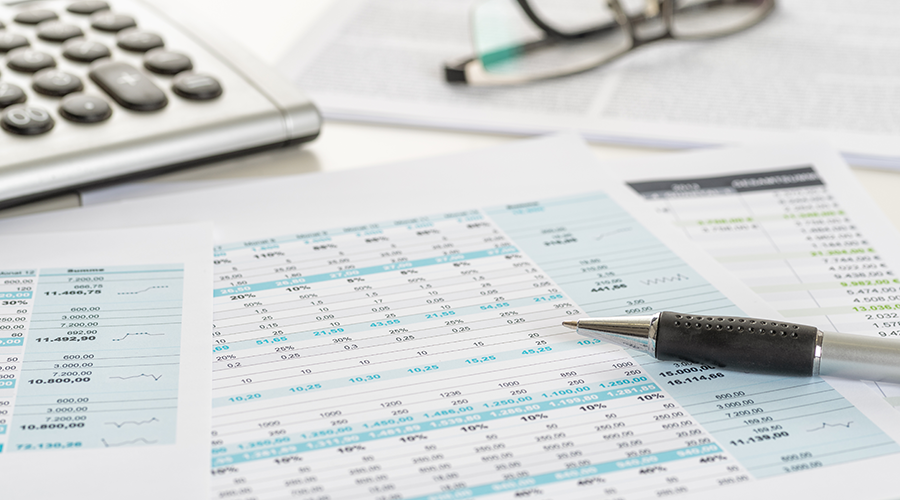
ファイナンスとは、英語で「finance」と表し、元々は財務や資金調達を意味する言葉です。
ファイナンスは企業・家計・政府など対象やシーンによって意味や使い方が異なるため、正確な意味がわかりにくいと感じている方も多いでしょう。
今回のコラムでは、ファイナンスの意味や会計・金融との違い、企業におけるファイナンス手法などについてわかりやすく解説します。
ファイナンスとは?英語の基本的な意味、会計・金融との違い
ファイナンスという言葉は、日常的にもビジネスの現場でも使われますが、その正確な意味や関連する用語との違いは意外と知られていません。
はじめにファイナンスという言葉の基本的な意味、金融・会計との違いについて確認しておきましょう。
英語のファイナンス(finance)とはどういう意味?
ファイナンスとは、英語の「finance」をカタカナ表記したもので、訳語としては「財政・財務・金融・資金調達」といった言葉が充てられます。
financeの語源は、ラテン語「finis」(終わり、境界)や「finire」(終わらせる、決済する)にあり、取引の終結や支払い、負債の清算を意味する言葉から、財政や金融全般という意味で使われるようになりました。*
英語では「to finance」という動詞で、資金を調達したり融通したりする、という意味でも使われます。つまり、企業や個人が必要なお金を集め、その資金をどのように活用するか、という行動がファイナンスの意味です。
*参考:EnglishBattle financeの語源と覚え方
ファイナンスと金融との違い
ファイナンスとよく混同される言葉に「金融」があります。金融の本来の意味は「お金を融通すること」です。
ファイナンスと金融の主な違いとしては、金融は、銀行や証券会社などが行う仕組みや制度を示す意味あいで使われることが多い一方、ファイナンスは「個人や企業の視点でお金をどう動かすか」を扱うという点が挙げられます。
つまり、金融が“仕組み”なら、ファイナンスはその“使い方”と捉えると、両者の違いが理解しやすいでしょう。
しかし、最近では日本の金融機関のことを、英語で「ファイナンス」または「ファイナンシャルカンパニー」と訳すことがあります。また、最近ネットでよく目にする「Googleファイナンス」や「ヤフーファイナンス」といったサイトは、株価や為替などの金融情報を掲載しており、一般的には「ファイナンス=金融」という意味で使われていることもあるので注意してください。
ファイナンスと会計との違い
ビジネスの分野では、ファイナンスと並んで「会計」という分野もありますが、ファイナンスと会計の違いはどのようなところにあるのでしょうか。
会計とは、企業の取引や資産を記録・整理し、財務諸表などの形で報告する「記録と報告の手法」です。これに対し、ファイナンスはその会計データをもとに「資金の使い方を考える分析・意思決定するやり方」だといえます。
例えば、会計が「どれだけお金が入ってきたか・出ていったか」を記録するのに対し、ファイナンスは「企業価値を高めるためにお金をどのように調達したり、投資したりすべきか」を判断します。また、会計は企業の「利益」を扱うのに対し、ファイナンスは「キャッシュ(現金)」を重視するという点も大きな違いです。
しかし、ファイナンスは会計データをもとに財務や投資の判断を行う必要があるのはもちろん、会計ではキャッシュフロー計算や財務諸表の項目が含まれており、両者の目的は異なるものの、補完的な役割にあるといえるでしょう。
会計と財務・経理の違いについては以下のコラムで解説していますので参考にしてください。
ファイナンスの使われ方|企業・個人・政府での意味の違い
ファイナンスは「資金をどのように集め、使い、管理するか」を扱う分野ですが、その使われ方は企業・個人・政府の立場によって異なります。
それぞれの目的と視点から、ファイナンスの意味を理解することが重要です。
ここでは、企業・個人や家庭・政府でのファイナンスの使われ方をそれぞれ解説します。
企業におけるファイナンス
企業におけるファイナンスには、狭義のファイナンスと広義のファイナンスの2種類があります。主に企業における資金調達を意味するのが狭義のファイナンスです。広義のファイナンスには、資金調達に加え投資や資本構成の判断など、企業価値を高めるための幅広い財務活動全般を意味します。
企業における広義のファイナンスは「コーポレートファイナンス」とも呼ばれ、以下のような項目が含まれます。
- 資金調達
- 利益の分配
- 投資判断
- キャッシュフロー管理
- リスクの測定
- 資本構成
- 企業価値の測定
銀行からの借入(デット)や株式発行(エクイティ)によって資金を集めるのはコーポレートファイナンスの重要な役割です。また、集めた資金をどのプロジェクトにいくら使うかを判断し、将来的な利益を最大化することも企業ファイナンスの目的の1つです。資金調達や投資判断を効率的かつ効果的に行い、企業価値を最大化するために、正しくリスクや企業価値を測定したり、最適な資本構成を考えたりすることもコーポレートファイナンスに含まれます。
このように、企業におけるファイナンスは、企業価値を最大化するための財務活動の総称であり、経営戦略の中核を成すものといえます。
家庭・個人のファイナンス(家計管理・資産形成)
ファイナンスは個人や家庭においても使われます。
個人や家庭におけるファイナンスとは、家計の収入と支出を管理しながら、貯蓄や投資によって資産を形成・運用することです。
従来の日本では、収入と支出の家計管理ばかりが注目されていました。しかし近年は、住宅ローンや消費者金融など個人の資金調達手段、あるいはNISAなど個人の投資手段が多様化するにつれ、個人や家庭におけるファイナンスの重要性がクローズアップされています。
企業のファイナンスは金銭に還元できる企業価値の最大化を目的としていますが、個人のファイナンスは金銭的利益だけでなく安心・安定した暮らしを守ることも大きな目的である点に違いがあります。
財政ファイナンスとは
財政ファイナンスとは、政府が中央銀行の力を借りて資金調達を行う仕組みを指します。
具体的には、国債を政府が発行し、それを日銀などが直接引き受けることで、財政支出に必要な資金をまかなう方法です。本来、財政ファイナンスはインフレや財政規律の崩壊を招く恐れがあるため、多くの国で禁止や制限の対象とされています。
日本でも財政法第5条により特別の事由がある場合を除いて、財政ファイナンスは禁止されています。
ファイナンスの手法・種類とその違い
企業や個人が資金を調達・活用するには、いくつかの異なる方法があります。
ここでは代表的な4つのファイナンス手法を取り上げ、それぞれの特徴と違いを紹介します。
デットファイナンス
デットファイナンスとは、銀行からの融資や社債の発行など、外部からお金を借りる形で資金を調達する方法です。
この方法の最大の特徴は、調達した資金の返済義務があることです。つまり、利息をつけて一定期間内に返す必要があります。
メリットとしては、株式を使わないため経営権を保てること、利息が経費扱いになるため節税にもつながる点が挙げられます。しかし、借入額が多いと返済負担が大きくなり、資金繰りに影響が出る恐れもあります。
エクイティファイナンス
エクイティファイナンスとは、株式を新しく発行して資金を集める方法です。調達した資金は返済する必要がありません。エクイティファイナンスは、上場企業の公募増資のほか、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家などから出資をしてもらう方法などがあります。
ただし、新しい株主が増えることで経営への影響力が分散し、意思決定に影響が出る可能性もあります。配当などの利益還元も求められるため、その分の準備も必要です。
アセットファイナンス(資産活用型)
アセットファイナンスとは、企業や個人が保有する資産を使って資金を調達する方法です。アセットファイナンスの方法としては、土地や建物の売却、ファクタリングや手形割引による売掛金の現金化などが挙げられます。
この方法の利点は、新たな借金をせずに現金を得られることです。売却後もリース契約を結べば、その資産を使い続けることも可能です。一方で、資産の所有権を手放すことになるというデメリットがあります。
リスクファイナンス(保険やヘッジ手法)
リスクファイナンスとは、自然災害や経済変動など、将来の予測できない損失に備えるための資金管理の方法です。
具体的には、自己資金で備えるほか、保険への加入や為替・金利の変動を抑えるヘッジ取引などがあります。メリットは、万が一のトラブルが起きた際でも企業活動が止まらないよう備えられる点です。ただし、保険料やヘッジ取引にはコストがかかるため、適切なリスクマネジメントとコスト管理のバランスが求められます。
ファイナンスを学ぶ方法と関連資格
ファイナンスは、企業の業種や規模を問わず事業活動や経営判断に欠かせない重要な知識です。
ビジネスの現場では、財務諸表の読み取りや資金計画の立案、投資効果の分析など、幅広い場面でファイナンスのスキルが求められます。
さらに、ファイナンスの考え方や知識は、個人や家計の分野にも活かすことも可能です。
こうした背景から、キャリアアップや転職を目指す人はもちろん、財務や経理畑ではないビジネスパーソンの間でも、ファイナンスを学び直す動きが高まっています。
最後に、ファイナンスを学ぶ人が増えている理由や、ファイナンスの基礎が学べる資格について解説します。
ファイナンスはキャリアアップや転職に活かせる知識
ファイナンスの知識は、キャリアアップや転職を目指すうえで有利に働きます。なぜなら、企業の経営判断や資金計画に関わる知識は、管理職や専門職に欠かせないスキルだからです。
特に、経営企画・財務・コンサルタントといった職種では、ファイナンスの理解があることで業務の幅が広がり、より戦略的な役割を担うことにつながるでしょう。
このため、ファイナンスについて本やセミナーで学んだり、ファイナンスに関わる資格を取得したりする人が増えています。
ファイナンスの基礎が学べる資格
ファイナンスを体系的に学ぶために、資格取得を目指す人も増えています。
ここでは、初心者でも挑戦しやすい、ファイナンスの基礎が学べる資格を4つご紹介します。
日商簿記
簿記検定はファイナンスの基礎となる会計知識が身につく資格です。簿記検定にはいくつか種類がありますが、なかでも日本商工会議所が運営する日商簿記は最もメジャーな資格であり、毎年10万人以上の人が受験しています。
初級から3級は複式簿記や商業簿記の基本、2級から工業簿記や原価計算などが加わります。1級は高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算、企業会計に関する法規を踏まえた経営分析などを学び、合格すると税理士試験の受験資格が得られます。日商簿記の受験資格に、学歴や取得資格などの条件はないため、基本的に誰でもどの級からでも受験することが可能です。
試験日が全国各地で同一日に施行する統一試験と、各ネット試験会場が独自に試験日を設定できるネット試験があります。
FP(ファイナンシャル・プランニング技能検定)
ファイナンシャル・プランニング技能検定は、顧客に対し貯蓄・投資など含めてあらゆるお金にまつわる問題・課題の相談にのりアドバイスをするための技能を検定します。
ファイナンシャル・プランニング技能士は1~3級まであり、金融財政事情研究会または日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)の実施する検定試験を受検し、合格した場合に授けられる国家資格です。
ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継などを対象に、学科試験と実技試験が行われます。
FASS(経理・財務スキル検定)
FASS(経理・財務スキル検定)とは、経理・財務分野における客観的な実務知識・スキルの習得度を測る検定試験です。経済産業省の委託を受けた日本CFO協会が運営しています。
検定試験を受けると合否判定ではなく、A~Eの5段階で評価が受けられるため、自分の実務レベルの判断をしたい場合にもおすすめです。経済産業省が開発した「経理・財務サービス・スキルスタンダード」をベースに、資産・決算・税務・資金の4分野で、業務知識や実務スキルに関する問題が出題されます。
参考:FASS 経理・財務人材育成事業|公式サイト検定の概要:FASS検定
証券アナリスト(CMA)
証券アナリストは、投資価値の分析・評価を行うためのスキルを身につけた投資分野のプロフェッショナル資格です。日本証券アナリスト協会所定の教育講座を受講したうえで、それに基づく試験に合格し、一定の要件を満たすことで日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)に認定されます。
約2.9万人のCMAのうち、投資運用・証券会社の所属が約38%、銀行や保険会社など金融系が約31%となっています。(2025年3月末現在)金融業界での取得者が多いものの、投資や金融だけでなく、企業財務やファイナンス理論まで体系的に幅広く学べるため、事業会社の財務担当者やコンサルタントなどにも人気の資格です。
まとめ|ビジネスや企業にファイナンス知識が求められている
ビジネスのあらゆる場面で、ファイナンスの知識は必要不可欠です。ビジネス環境が複雑化し、資金調達手段も多様化する中、ファイナンスの基礎を正しく理解し、なおかつ最新の情報をアップデートすることが求められています。
ファイナンスは単なる資金調達やキャッシュフロー管理だけでなく、投資判断、リスク管理、企業価値測定など、企業活動の根幹を支える考え方です。このため、経営層は必ずファイナンスについて理解する必要があり、部署や職種を問わず、職位が上になるほどファイナンスの知識が重要になるといえます。
今後さらに複雑化する経済環境の中で、ファイナンスを正しく理解し、活用できる人材の価値はますます高まっていくでしょう。

