バッファとは?ビジネスにおける意味、使い方と管理方法「PPCM」
 更新日:2025.04.25
更新日:2025.04.25
 公開日:2024.08.29
公開日:2024.08.29
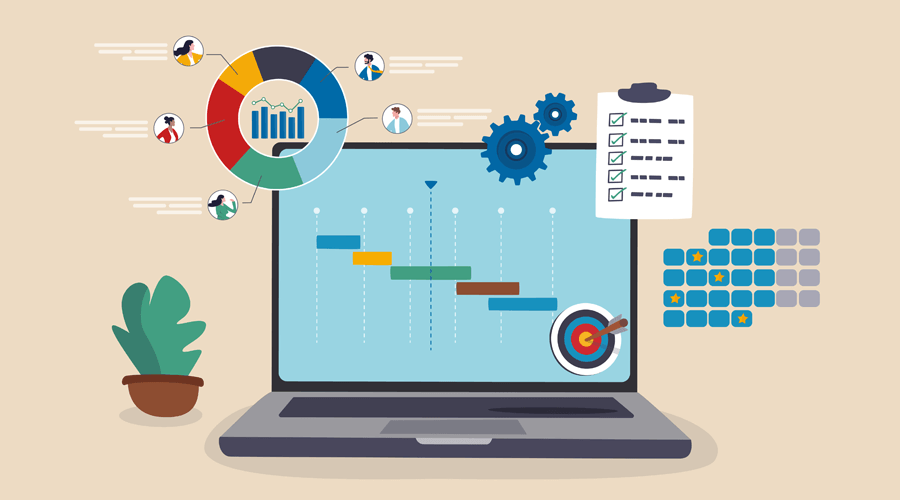
バッファ(バッファー)には、様々な意味があります。プロジェクト管理や工程管理に関わるビジネス用語としては「時間的余裕」「衝撃を和らげるもの」などの意味合いで使われますが、業界によって異なるニュアンスをもっています。
本コラムでは、一般的なビジネス用語としてのバッファを中心に、バッファという言葉の使い方、バッファを持たせるメリット、バッファ管理手法である「PPCM」の考え方と管理手順を解説します。
バッファとは?バッファの英語・日本語での意味
バッファという言葉自体は、英語の「buffer(緩衝材、緩和物)」から来ています。「バッファー」と表現されることもあります。
一般的なビジネス用語としてのバッファや業界用語としてのバッファを理解するには、これに加えて次の意味合いをおさえておくとよいでしょう。
- 緩衝:対立しているもの同士の間に入って、不和・衝突を和らげること
- 緩和:厳しさや激しさを和らげること
バッファは、もともとIT用語で「コンピュータ内で一時的な情報を保存する領域」を意味する言葉として用いられてきました。現在は、「余裕・ゆとり」や人・組織同士の関係性を「和らげるもの」といった意味合いで、ビジネス用語として広く使われています。
バッファのビジネス一般における意味と使い方
一般的なビジネス用語としてのバッファには、
- 時間的・物的な「余裕」「ゆとり」
- 衝突や不和を和らげる「緩衝」
の2つの意味があります。表現の使い方とともに見ていきましょう。
(1)時間的・物的な「余裕」「ゆとり」の意味での使い方
1つ目の「余裕」「ゆとり」の意味でのバッファは、主にプロジェクト管理においてスケジュール・予算・人員・在庫などに余裕を持たせるときに使います。
具体的な使い方には、
「スケジュールにバッファをとる」
「納期にバッファを持たせる」
「予算にバッファを設ける」
「在庫バッファを確認する」
などがあります。
「納期にバッファを持たせる」とは、成果物が納期に間に合うよう、時間的余裕を持たせるという意味。「在庫バッファ」は、在庫切れを防ぐための余分な在庫のことです。
(2)衝突や不和を和らげる「緩衝」の意味での使い方
2つ目の「緩衝」の意味でのバッファは、簡単に言えば組織や人間関係における仲介役・サポート役のことです。
具体的な使い方としては、
「開発チームと営業チームのバッファの役割を果たす」
「契約交渉においてバッファになる」
などがあるでしょう。
いずれも、両者における衝突や摩擦を緩和したいときに使います。
バッファを持たせる3つのメリット
スケジュールやリソースにバッファを持たせることには、主に3つのメリットがあります。
リスクマネジメントの強化
1つ目のメリットは、バッファの確保がリスクマネジメントになることです。
仕事にかけられる時間やリソースにあらかじめバッファを持たせておけば、プロジェクトの途中で予期せぬ事態が発生しても冷静に対処できます。予備の時間を使ってトラブル解決に向けた調整を行ったり、予備の原料や人員によって補充されるタイミングを待つことなく対応を進めたりできるからです。
バッファを使うことで、最終成果物の品質低下や納期遅れのリスクを軽減できます。
業務の効率化
2つ目のメリットは、業務効率化です。スケジュールにバッファを持たせることで、仕事全体に余裕が生まれるからです。
トラブルなどが発生していない状況でも、何らかの理由により、特定のタイミングで業務が集中してしまうことはあります。バッファを確保していれば、そうしたときに人員や設備といったリソースの再配分を柔軟に行い、ピーク時の過負荷を軽減できるでしょう。
業務量や負担の急激な変化を和らげ、プロジェクト全体を安定させながら効率よく進められます。
パフォーマンスの向上
3つ目は、メンバーのパフォーマンス向上です。
時間に追われたり使えるリソースに余裕がなかったりすれば、メンバーは常に時間・リソースの不足を心配しなければなりません。そうした心に余裕のない状況では、焦りからミスが生じやすくなってしまいます。
しかし、時間やリソースにバッファを持たせておけば、多少のミスがあっても取り戻すための時間的・物的余裕が生まれます。メンバーも落ち着いて仕事を進められるため、ミスの減少やストレス軽減につながるでしょう。結果として、全体のパフォーマンス向上が期待できます。
さらに、タスク管理の面でのバッファを確保するだけでなく、メンバーのスキルアップやコミュニケーションのための時間も確保できれば、チームの活性化とさらなるパフォーマンス向上が望めます。
バッファを設定する際の2つの注意点
バッファは、プロジェクトを円滑に進行させるために欠かせない要素。ただし、適切に設定しなければ逆効果になる場合もあります。バッファを設定する際は、2つのポイントに気をつけましょう。
プロジェクト全体で一元管理する
大規模なプロジェクトの場合、バッファはタスクごとに設けるのではなく、プロジェクト全体で一元管理することが大切です。バッファの一元管理によって、各工程終了時のバッファの残量を確認しやすくなるからです。
バッファを一元管理していれば、一部のタスクで遅延やトラブルが生じても慌てる必要はありません。最終的なスケジュールを見据えながら、時間・人員・設備などで柔軟な対応ができるからです。
バッファの一元管理の方法について、詳しくは「CCPM」という管理手法の項目で解説します。
バッファの量の設定は慎重に判断する
バッファの量は、過去のデータをもとに予測し、過不足なく設定する必要があります。
「どのタスクについてどのくらいのバッファを取るべきか」という判断は難しく、必ずしも一律に決められるものではありません。また、これまで行ってきた同様のタスクの所要時間を記録していない場合、予測を立てること自体が難しいでしょう。
それでも、1日に進められる現実的な量を計算し、トラブルが発生した場合の対応に必要な時間を見積もることは重要です。バッファが少なすぎると、本来バッファを設けることで得られるメリットを十分に得られませんし、バッファが多すぎても余計なコストがかさんでしまうからです。
テンポよくプロジェクトを進めていくためにも、バッファの量は事前によく精査して決定するとともに、今後のために時間やリソースについて記録を取っておきましょう。
バッファ管理手法「CCPM」とは?バッファの種類と活用メリット
設定すべきバッファの量を見積もり、実際に管理していく手法には、「CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)」があります。
CCPMとは、プロジェクトを効率的に進めるためにバッファを一元管理するもの。その特徴や用語、設定すべきバッファの種類などをおさえておくと、バッファを管理しやすくなります。
CCPMの特徴とクリティカルチェーン
CCPMの特徴は、プロジェクト管理において「個々のタスクの流れや関係性」と「時間・人・設備などのリソースの制限」の両方に注目し、優先順位をつけて管理していく点です。例えば、「Aの作業を終えてからでないとBの作業ができない」「リソースαはタスクAとタスクCの両方で使う」などの依存関係を踏まえて、タスクに取り組む順番や同時進行が可能か否かを検討します。
そのようにして明らかになった工程の中で、最も時間がかかる重要なタスクの流れは「クリティカルチェーン」と呼ばれます。プロジェクト全体の期限に間に合わせるには、このクリティカルチェーンが納期までに完了するように調整しなければなりません。
このクリティカルチェーンに組み込まれる時間的余裕が、CCPMにおけるバッファです。バッファは全ての工程の最後にまとめて設定され、タスクごとのバッファはありません。「なるべく早く効率的にタスクを完了させる」ことを前提として、それでも予定の時間を超えてしまった際にプロジェクト全体に設定されたバッファを少しずつ使っていくイメージです。
CCPMにおけるバッファの種類
CCPMで設定されるバッファには、3種類のバッファがあります。「プロジェクトバッファ」「合流バッファ」「リソースバッファ」です。それぞれの意味は、下表の通りです。
【CCPMにおける3種類のバッファ】
| バッファの種類 | 概要 |
|---|---|
| プロジェクトバッファ |
|
| 合流バッファ |
|
| リソースバッファ |
|
なお、合流チェーンとは、例えば「会議室を予約する」「資料印刷のためのコピー用紙を確保する」などの付随的なタスクの流れです。
合流チェーンは、並行的に進められるとはいえ、最終的には全てクリティカルチェーンに合流します。会議室の予約で言えば、“会議室を予約することで、展示会参加に向けた打ち合わせを実施できる”といった具合です。
合流バッファは、この合流チェーン自体における最終タスクと、合流チェーンがクリティカルチェーンに合流すべき期限との間に設定されます。
CCPMによるバッファ管理のメリット
CCPMの手法に基づくバッファ管理のメリットは、これまでに述べてきたバッファを設けるメリットと重なります。
【CCPMにおけるバッファ管理のメリット】
| メリット | 概要 |
|---|---|
| トラブルに強い |
|
| スケジュールが明確になる |
|
| 無駄が少ない |
|
時間的・物的な余裕をまとめて管理するというCCPMの手法は、各タスクにおける遅れや不足がプロジェクト全体にどのような影響を与えるかを容易に可視化してくれます。つまり、プロジェクトにおける無駄を削減しつつ柔軟な対応を可能にし、プロジェクト全体を俯瞰的に管理しやすい点が、CCPMの大きな魅力なのです。
CCPMの手順とバッファ管理の方法
こうしたCCPMを効果的に進めるには、次の6つのステップで考えるとわかりやすくなります。
- (1)プロジェクトの目的・目標を明確にする
- (2)タスクを細分化する
- (3)大まかな所要時間を算出し、クリティカルチェーンを見つける
- (4)各タスクに必要なリソースを算出する
- (5)バッファを設定する
- (6)進捗管理においてバッファの残量を管理する
1つずつ見ていきましょう。
(1)プロジェクトの目的・目標を明確にする
プロジェクトの具体的な流れやスケジュールを作成するには、まず「なぜやるのか」「ゴールはどこか」といった目的・目標の設定が重要です。
目的は、新規事業の立ち上げや既存事業の課題解決、新規顧客獲得のための施策など様々。会社全体の経営戦略や事業戦略を踏まえつつ、プロジェクトの目的を明確にしましょう。
目標については、「売上げを向上させる」のような漠然としたものではなく、「どの指標を使ってどのくらいのレベルを達成するべきか、いつまでに達成するべきか」という具体的で数値化された基準と期限の設定が必要です。
目標設定のフレームワークには、例えば「ODSC」や「SMARTの法則」があります。
【ODSCの内容】
| 頭文字 | 意味する項目 | 概要 |
|---|---|---|
| O | Objectives(目的) | プロジェクトの目的を定める |
| D | Deriverables(成果物) | そのプロジェクトで生み出す成果物の種類・特徴・数量などを定める |
| SC | Success Criteria(成功基準) | 期限と達成すべき状態や数値目標を定める |
【SMARTの法則の内容】
| 頭文字 | 意味する項目 | 概要 |
|---|---|---|
| S | Specific(明確性) | 誰が見ても同じ解釈ができるよう、具体的な目標を設定する |
| M | Measurable(測定可能) | 定量的な監視ができるよう、測定可能な数値目標を設定する |
| A | Achievable(達成可能) | 現実的に達成可能な項目と数値を設定する |
| R | Related(関連性) | 設定しようとする目標と経営戦略における目標との間に関連性をもたせる |
| T | Time-bounded(適時性) | 目標の達成期限を設定する |
ODSCは主に事業を始める段階で使える一方で、SMARTの法則は目標設定が必要な様々なビジネスシーンで有用です。SMARTの法則については、以下のKPIマネジメントに関する記事でもご紹介していますので、ぜひご確認ください。
コラム「KPIとは?簡単にわかるビジネスでのKPIマネジメントとKPI設定のコツ」はこちら
(2)タスクを細分化する
プロジェクト全体の流れと明確な期限・目標の設定ができたら、次は取り組むべき業務の明確化です。
例えば、新商品を市場に投入したり既存の商品・サービスの売上げを伸ばしたりするには、自社のWebサイト更新やプレスリリースの公開、リスティング広告の活用、展示会への参加など、多様な手法・工程が考えられます。
こうした施策で取り組むべき業務を特定し、その業務で必要な作業を最も小さなタスクレベルまで細分化しましょう。「これ以上は細分化できない」というレベルまで小さくすると、担当するメンバーが行動に移しやすくなるだけでなく、現実的な所要時間を見積もることができます。
もし「展示会への出展は、はじめてで所要時間がわからない」など、これまで経験のない業務があっても、「展示会ブースのデザインを外注できる業者の選定」「ブースデザインの打ち合わせ」「ブースの施工にかかる期間」といった具体的な工程をなるべく細かく洗い出すことが重要です。
(3)大まかな所要時間を算出し、クリティカルチェーンを見極める
次は、各タスクの大まかな所要時間を算出し、それをもとに「クリティカルチェーン」を見極めましょう。
こうして洗い出したタスクには、「タスクAが終わったらタスクB」のような依存関係があります。同時並行的に進められるものもあるでしょう。しかし、CCPMで重要になるのは依存関係のあるタスク同士の流れです。
例えば、展示会に参加して新商品をアピールするには、そのための場所(ブース)が必要です。ブースを設置するには、ブースを建てなければなりません。そして、ブースを建てるには、「どのようなブースを建てるか」というデザインが不可欠です。“前のタスクが終わらなければ次のタスクを始められない関係”ですので、並行的に進めることはできません。
このような依存関係にあるタスクの流れは、1つとは限りません。ブースのデザイン・施工期間に、展示会で使用するチラシのデザイン・印刷を進めることがあるからです。
そこで、複数のタスクの中で最も所用時間(期間)が長いものをクリティカルチェーンと定め、これが期限を過ぎないように管理する必要があります。
(4)各タスクに必要なリソースを算出する
クリティカルチェーンの見極めと同時、あるいは見極めたあとに、より詳細なリソースの算出を行いましょう。
具体的には、これまで注目してきた所要時間のほか、目標達成のために必要な設備・ツール・材料の種類・数量・使用期間、各タスクを遂行する人員として必要な人数などです。休暇でメンバーが欠勤する可能性も踏まえて、プロジェクト完遂に必要なリソースを十分に確保してください。
もし設備や人員が不足する場合、タスク遂行のタイミングをずらすことで解決できるか否かも検討しましょう。
(5)バッファを設定する
ここまでの準備を終えたら、いよいよバッファを算出します。バッファとしてどのくらいの時間やリソースの余裕が必要かは、可能な限り過去のデータに基づいて判断しましょう。
時間的余裕を検討する際にそうしたデータが得られない場合は、まず所要時間の1〜2割をバッファに当てる方法もあります。つまり、もともと算出していた所要時間を削って「なるべく早くタスクを終わらせる」という前提を置き、削った分の時間をバッファとして確保しておく方法です。
当然ながら、一律1〜2割で削ることがタスクの性質上好ましくない場合もあります。そうしたケースでは、作業の内容や手順を吟味し、最短で終わらせられる時間と、トラブルが発生した場合の解決・タスク完遂にかかる時間を計算し、その差分をバッファとしましょう。
時間的余裕としてのバッファを組み込む位置は、全てのタスクが終わってからプロジェクトの期限を迎えるまでの期間、もしくはクリティカルチェーンと合流チェーンが交わる地点の合流チェーンの末尾です。
(6)進捗管理においてバッファの残量を管理する
プロジェクトの進行中にバッファ管理として行うべきことは、現時点でどのくらいのバッファを消費し、どのくらいのバッファが残っているかを確認することです。
たとえ各タスクの所要時間を無駄・無理のない範囲で設定していても、スケジュール通りにタスクが進むことはなかなかありません。そのため、プロジェクトマネジメントを担うマネージャーは、常に残りのバッファを確認する必要があります。クリティカルチェーンの最後のタスクを期限前に完了できるようメンバーとコミュニケーションをとり、指示を出しましょう。
バッファを確認する際は、表計算ソフトに「どのタスクでどのくらいバッファを消費したか」を記録しておくと、その後のプロジェクトにおけるバッファ管理で参照できます。
バッファのIT業界用語・金融業界用語としての意味
以上の一般的なビジネス用語のバッファとは別に、業界用語として使われている「バッファ」もあります。時間や在庫に余裕をもたせるという意味合いでは理解しにくい「バッファ」に直面した場合は、業界の専門用語かもしれません。
典型的にはIT業界や金融業界におけるバッファがあり、建築業界や製造現場などでも「バッファ」を用いた表現が使われています。
本コラムの最後に、IT業界と金融業界におけるバッファの例をご紹介しましょう。
コンピュータ・IT業界におけるバッファの意味
コンピュータ・IT業界用語としてのバッファには、「データバッファ」や「バッファメモリ」「ネットワークバッファ」「バッファサイズ」といった用語があります。それぞれの大まかな意味は、下表の通りです。
【コンピュータ・IT業界におけるバッファの例】
| 用語 | 概要 |
|---|---|
| データバッファ |
|
| バッファメモリ |
|
| ネットワークバッファ |
|
| バッファサイズ |
|
コンピュータ・IT業界でのバッファは、データの送受信とスムーズな処理において重要な役割を果たすものです。
IT用語のバッファと「キャッシュ」「キュー」の違い
IT用語としてのバッファは、「データを一時的に保存する」という意味で「キャッシュ」や「キュー」と似ている部分があります。しかし、これら3つの用語には、根本的な違いがあります。
まず、バッファとキャッシュの違いは、その目的です。バッファは、前述のようにデータの流れをスムーズにすることを目的とする、入出力に関連するものです。他方、キャッシュの目的は、データの一時保存によってそのデータを再利用し、よくアクセスするデータをより高速に取得することです。
バッファは「データの一時保存のための領域」、キャッシュは「再利用するために一時保存されたデータ」と言い換えてもよいでしょう。
バッファとキューの違いは、データの扱い方です。キューとは、“最初に登録されたデータが最初に取り出される”という一時保存領域の構造のこと。データに順番をつける“First-in, First-out”が特徴で、人気店にできる順番待ちの列のイメージです。これに対し、バッファにはそのような構造はありません。
ただ、「リングバッファ」という言葉があり、これには注意が必要です。リングバッファとは、キューに使われる一時保存領域とその構造を意味します。イメージとしては、円形に並べられた椅子に人が座っており、時計回り(または反時計回り)に順番に人が呼ばれて立つと、そこに新たな人がまた順番に座っていくというものです。キューに使う領域が枯渇する問題に対応するための方法として活用されています。
金融業界におけるバッファの意味
金融業界におけるバッファの代表例は、「資本保全バッファー」「カウンターシクリカル・バッファー」「G-SIBs/D-SIBsバッファー」です。これらは、国際金融システムをより健全なものとするための指針である「バーゼル3」によって導入されました。
なお、コンピュータ・IT業界では「バッファ」と表記しますが、金融業界では「バッファー」とするのが一般的です。
「資本保全バッファー」「カウンターシクリカル・バッファー」「G-SIBs/D-SIBsバッファー」の概要は、以下の通りです。
【金融業界におけるバッファの例】
| 用語 | 概要 |
|---|---|
| 資本保全バッファー |
|
| カウンターシクリカル・バッファー |
|
| G-SIBs/D-SIBsバッファー |
|
金融業界におけるこれらのバッファは、いずれも「重要な金融機関が破綻しないように余分な資本を蓄えておこう」というものです。
2024年10月の時点で、日本のG-SIBs/D-SIBsには以下の金融機関が指定されています。*
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ
- みずほフィナンシャルグループ
- 三井住友フィナンシャルグループ
- 三井住友トラストグループ
- 農林中央金庫
- 野村ホールディングス
- 大和証券グループ本社
バッファ管理はCCPM+KPI/KGI管理で効果的に
一般的なビジネス用語としてのバッファの管理は、プロジェクトを安定的に進めるキーポイントです。CCPMの手法とともにKPIやKGI管理を実践することで、より確実な目標達成につなげられるでしょう。
多くの企業の人材育成をご支援してきたALL DIFFERENTでは、現場の目標達成やプロジェクトマネジメントに役立つ管理職向け研修をご提供しています。今回ご紹介したバッファ管理手法であるCCPMでは、具体的で定量的な指標による目標設定と適切なタスク分解が重要。これらを学べる研修として、WBS作成によるプロジェクト管理を理解する研修と、目標達成に向けたKPI/KGI管理のノウハウを学べる研修をご用意しました。目標達成にお悩みの管理職の方、管理職の育成研修をご検討中の方は、ぜひご活用ください。
「【IT業向け】はじめてのプロジェクト管理シリーズ<WBS作成編>」研修の詳細はこちら
「組織目標を達成するための指標の立て方~管理職研修~」の詳細はこちら
組織の課題が明確になっている場合は、その課題に合わせて研修プログラムを作成・実施する講師派遣型研修もおすすめです。どうぞお気軽にお問い合わせください。

