トランジションとは?キャリア理論における意味・具体例・乗り越え方
 更新日:2025.10.30
更新日:2025.10.30
 公開日:2023.04.18
公開日:2023.04.18
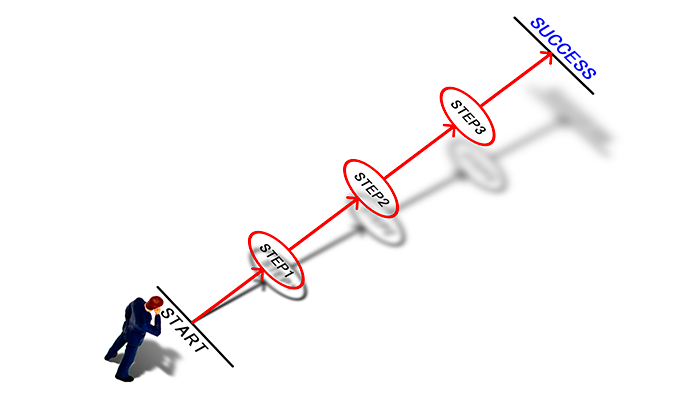
トランジションとは、英語で「移行」や「変化」を意味する言葉で、ビジネスでは昇進や異動などで役割が変化するキャリアトランジションが注目されています。
本コラムでは、トランジションの意味やビジネスでキャリアトランジションが注目されている理由、代表的な理論などについてわかりやすく解説します。
トランジションの意味とは?文脈ごとの使われ方を理解する
トランジションの英語の意味は「移行」や「変化」「切り替え」などですが、ビジネスやキャリアにおいては役割や環境の変化を、映像ではシーンの切り替えを意味するなど、分野ごとに使われ方に違いがあります。
まずは、トランジションの一般的な意味から、ビジネス・映像・スポーツといった分野ごとの具体的な用例までを整理しておきましょう。
一般的な意味と語源
トランジションとは、「移り変わり」「移行」「過渡期」を意味する言葉です。語源はラテン語の「transitio(移動、通過)」で、英語では“transition”と表記されます。
例えば季節の変わり目や、学生から社会人になるときの心境の変化などにも使われます。
つまり、トランジションとは、何かが終わり、次の段階へと進んでいく「つなぎの期間」を表現する際に用いられる言葉なのです。
ビジネス用語としての「トランジション」の意味
ビジネスの現場では、トランジションは「役割の転換」や「組織変革」の過程を指す用語として使われます。例えば、プレイヤーからマネージャーへの昇進、新部署への異動、業務の引き継ぎなどが該当します。
こうした変化には、業務内容だけでなく、求められるマインドセットの転換も伴います。そのため、トランジションの期間には心理的な戸惑いや混乱が生じやすく、個人にも組織にも適切なサポートが求められるのです。
トランジションは、単なる作業の移行ではなく「行動と意識の転換」を含む重要なプロセスといえます。ビジネスにおいてトランジションが重要視される理由については、後ほど詳しく解説します。
映像・動画編集におけるトランジションの使い方
映像・動画編集においてトランジションとは、カットとカットの間を自然につなぐための効果のことを指します。
例えば、朝から夜への時間の経過を表すときにフェードアウトで場面を切り替えることで、視覚的にスムーズな演出が可能です。
このように、動画編集の分野では「つなぎの演出」としてのトランジションが重要な役割を果たします。
参考: Adobe|トランジションの意味や役割を知り、動画編集に役立てよう
スポーツ(サッカーやバスケ)でのトランジションの定義
スポーツ、とくにサッカーやバスケットボールにおけるトランジションは、「攻撃から守備、守備から攻撃への切り替え」の瞬間を指します。
ボールを奪った直後や失った直後の数秒間における動きが勝敗に直結するため、この「切り替えの速さ」が戦術的に重視されるのです。
近年では「トランジションの質」を高めることが、サッカーやバスケのチーム全体のパフォーマンス向上に不可欠とされています。
参考:スポジョバ|【サッカー】トランジションの意味とは?ネガティブってなに!?
トランジションファイナンスとは
脱炭素社会の実現に向けて、段階的に温室効果ガスの排出を減らしていく取り組みを支援する金融手法が「トランジションファイナンス」です。
特に排出量の多い産業にとっては、一足飛びに「グリーン」な状態を実現することは難しく、現実的な技術導入や投資が必要です。ここでのトランジションは「段階的な移行」という意味で使われています。
このような背景のもと、日本では政府(金融庁・経産省・環境省)が連携し、「トランジションファイナンスに関する基本指針」を策定しました。企業が長期的な脱炭素戦略に基づいて着実な排出削減を進める場合、その取り組みに対して資金提供を行う仕組みが整えられています。
キャリアトランジションの意味と注目すべき理由
ビジネスにおいてキャリアにおけるトランジションを特に「キャリアトランジション」と呼びます。
近年では、企業は以下のような理由から社員のキャリアトランジションに注目しています。
- 人材の離職防止と定着
- 効果的な人材育成と再配置
- 組織の生産性維持・向上
予測不能なVUCAの時代、企業は市場の急激な変化に対応するため、課題解決を意識した人材の再配置をより積極的に行わなければなりません。すると、多くの社員がトランジションに直面することになります。
再配置の対象となった社員が新しい役割に適応するには、役割を果たすための知識・スキルを習得し、新しい価値観に対応する必要があるでしょう。トランジションに直面する本人にとっては、非常に苦しい期間です。会社が何もサポートを行わなければ、役割の変化を受け入れられず、離職してしまうかもしれません。
さらに、労働力人口の減少が続く日本では、「自社が求める人材を採用できない」という課題を抱える企業が増えています。また、人材の流動化で「終身雇用が当たり前」という前提も通用しなくなってきました。
こうした背景から、人材を確保しながら急激な変化に対応するには、キャリアトランジションに直面する社員を会社全体でサポートする仕組みが必要なのです。組織の生産性の維持や向上のために、企業が社員のトランジションに積極的に関与することが求められています。
トランジションの具体例と直面しやすい問題
キャリアトランジションの代表例は、管理職・リーダー職への昇進・昇格です。一方で、妊娠・出産・育児・介護といった社員自身のライフステージの変化によるトランジションも無視できません。
ここでは代表的なトランジションの具体例と、そこで直面しやすい問題を紹介します。
管理職・リーダー職への抜擢
職場でリーダーや管理職に昇進することは、大きなキャリアの転機です。
新たな役割を任されることは期待の表れですが、同時に大きなプレッシャーも伴います。部下を持つ立場になれば、それまで自分の仕事だけを考えていればよかったものが、チーム全体の進捗管理マネジメント、さらには人材育成も考えなければなりません。その際、コミュニケーションの難しさや孤独感、意思決定の重さに戸惑う人も多いでしょう。
チームのマネジメントに失敗すれば、チーム全体の労働生産性が低下し、組織目標を達成できない恐れがあります。ひいては、管理職・リーダー職としての自信を失い、メンタルヘルスに支障を来してしまうかもしれません。
このような管理職・リーダーへの抜擢の場面では、社員がマネジメントの知識や自分の強みを再認識し、周囲の支援を受けながら少しずつ役割に慣れていくようにすることが重要です。
妊娠・出産・育児・介護などライフステージの変化
会社での異動、昇進・昇格がない場合でも、社員のライフステージの変化でトランジションが発生することがあります。
例えば、出産や育児、親の介護といったライフイベントは、働き方に大きな影響を及ぼします。これらの出来事は仕事と家庭のバランスを再構築するきっかけになりますが、同時に「両立の難しさ」や「キャリアの停滞」といった不安も生じやすくなります。
会社側の支援や配慮がなければ、不本意な形での退職となるリスクもあります。「誰にも頼れない」「誰も手伝ってくれない」という状況が続く場合、心身の疲弊と強い孤独感を招いてしまうでしょう。
このような時期には、柔軟な働き方の選択や、周囲との協力体制の確立が欠かせません。本人の意識だけでなく、職場全体で支え合う環境づくりがトランジションを成功させるカギになります。
サビカスのキャリア構築理論とトランジション
サビカスのキャリア構築理論とは、キャリア指導とカウンセリングを専門とするアメリカの研究者マーク・L・サビカス氏が提唱した理論です。
キャリア構築論では、キャリア形成として職業的パーソナリティ、キャリア適合性、ライフテーマの3つを重視します。
| 職業的パーソナリティ | 個人のキャリアに関連する能力、ニーズ、価値観、関心 |
|---|---|
| キャリア適合性 | 現在あるいは直近の職業的発達課題、職業的移行、個人的トラウマなどに対処するための個人のレディネスおよびリソース |
| ライフテーマ | 職業生活のもっとも主観的な部分に関わるものであり人々の職業行動に意味を与え、なぜその仕事で働くのかを明確にする価値 |
キャリアトランジションに際し、多くの人は従来の考え方や習慣を大きく揺さぶられます。
このようなキャリアトランジションの場面でサビカス理論を応用し、職業的パーソナリティ・キャリア適合性・ライフテーマといった重要な要素を考慮に入れながら、自身のキャリアを見直すことが大切です。
参考: Mark Savickas| About Mark L. Savickas
参考:労働政策研究・研修機構(JILPT)|新時代のキャリアコンサルティング[増補版]―現在と未来、理論と実践をつなぐ新たな架け橋―
トランジションの理論と段階モデル
誰もが直面し得るトランジションですが、全員がこの転機を順調に乗り越えられるとは限りません。転機を受け入れ、次のステージに進むにはどうすればよいか、様々な研究が行われてきました。
そうしたトランジション研究のうち、代表的なものが、ブリッジズのトランジション理論、ニコルソンのトランジション・サイクル・モデル、シュロスバーグのトランジション理論です。
3つのトランジションの理論と段階モデルについて解説します。
ブリッジズのトランジション理論
アメリカの組織運営コンサルタントであるウィリアム・ブリッジズは、プロセスを3段階に分けて捉えるトランジション理論を展開しました。
その3段階とは、「終焉(Endings)」「中立圏(Neutral Zone)」「開始(New Beginnings)」です。
【ブリッジズのトランジション理論】
| 終焉(Endings) |
|
|---|---|
| 中立圏(Neutral Zone) |
|
| 開始(New Beginnings) |
|
トランジションは役割の「終焉」から始まるとする点が、ブリッジズの理論の特徴です。中立圏を終えるには長い期間が必要なため、本人がじっくり向き合えるように見守る必要があります。
中立圏で十分な時間をかけて自分と向き合うことで、自らの目的や役割、そしてどのように貢献・参加すれば最も効果的かを理解して次の段階を開始する(New Beginnings)ことができるのです。
参考:-William Bridges Associates |Bridges Transition Model
ニコルソンのトランジション・サイクル・モデル
イギリスの心理学者、ナイジェル・ニコルソンによるキャリアトランジションの理論は、「トランジション・サイクル・モデル」と呼ばれます。
トランジションを「準備」「遭遇」「順応」「安定化」という4段階に分け、それらを循環させていくモデルです。
【ニコルソンのトランジション・サイクル・モデル】
| 準備(Preparation) |
|
|---|---|
| 遭遇(Encounter) |
|
| 順応(Adjustment) |
|
| 安定化(Stabilisation) |
|
トランジションを1回きりのイベントとして捉えるのではなく、その後のキャリアに続く連続したプロセスの一部として捉えることで、より前向きな取り組みが可能となります。
周囲の支援では、トランジションに直面している本人がどの段階にあるかを見極めることが、具体的な施策のヒントになるでしょう。
参考: Marcr |Transition Cycle - N. Nicholson and M. A. West
シュロスバーグのトランジション理論
アメリカのカウンセラー教育の研究者であるナンシー・K・シュロスバーグのトランジション理論でも、ブリッジズのように3段階に分けて捉えます。
シュロスバーグの理論の特徴は、トランジションの種類や文脈などを見定めたうえで、対処するための方法として「4つのS」の観点を提唱したことでしょう。
【シュロスバーグのトランジション理論の大枠】
| 転機を見定める |
|
|---|---|
| リソースを点検する |
|
| 転機を受け止め、対処する |
|
シュロスバーグの理論で最も重要な「4つのS」をまとめると下表のようになります。
【シュロスバーグの「4つのS」】
| 状況(Situation) |
|
|---|---|
| 自己(Self) |
|
| 支援(Support) |
|
| 戦略(Strategy) |
|
シュロスバーグの理論では、トランジションで注目すべき具体的な要素を確認できます。
トランジションに直面する本人にとっても、上司や同僚にとっても、「今何が必要か」を知る大切な手がかりとなるでしょう。
トランジションの乗り越え方5ステップ
では、ご紹介した3つのトランジション理論を踏まえて、トランジションの乗り越え方を具体的に見ていきましょう。
社員がキャリアトランジションを乗り越える際、企業側がどのようなサポートができるのか、という点を踏まえながら5つのステップに分けて解説します。
(1)トランジションのタイプを分析する
最初に行うべきは、今社員が直面しているトランジションのタイプを明確にすることです。
自分の意思で起きた変化なのか、それとも周囲の環境によって強いられたものなのかによって、必要な対処は大きく異なります。
トランジションを経験する社員自身が状況を正しく理解することで、感情の整理がつきやすくなり、次に取るべき行動も見えてくるでしょう。
分析に当たっては、アメリカの心理学者であるエドガー・H・シャインが提唱した「キャリアアンカー」「キャリアサバイバル」という観点が参考になります。
【キャリアアンカー、キャリアサバイバルとは】
| キャリアアンカー |
|
|---|---|
| キャリアサバイバル |
|
本人が自己イメージを明確に持ちつつ、周囲から期待される役割を認識することが、トランジションを主体的に乗り越えるポイントです。
トランジションから得られるメリットと生じ得るデメリットの分析、本人がどう感じているのかなどを確認することで、その後の行動計画の基盤となります。
(2)使えるリソースを確認する
次に、新しい役割の受容に向けて利用できる「リソース(資源)」を棚卸ししましょう。
会社として実施できるサポートは、社員が利用できる制度を知らせ、上長や人事担当者との1on1ミーティングを設定したり、具体的な業務支援をしたりすることです。
具体的には、仕事関連であれば横のつながりを強化する交流会の開催、自己啓発支援制度や社内で蓄積しているノウハウへのアクセス方法の周知、などが挙げられます。
家庭生活で生じたトランジションの場合は、各種の休暇制度・休職制度・手当、時短制度やテレワーク制度など、仕事とプライベートの両立に活用できる制度を教えてあげるとよいでしょう。
メンタルヘルスへの配慮や保健スタッフとの面談機会なども、必要に応じて設けてください。
(3)変化を受容し、適応に必要な知識・スキルなどを特定する
次のステップは、変化の受容です。ブリッジズであれば「開始」の段階、シュロスバーグであれば「リソースを点検する」段階が該当するといえます。
最初のステップでもトランジションに直面した社員本人の自己分析を行いますが、受容に向けたこの段階では、より定量的に知識・スキルの確認を行い、新しい役割に必要な能力の習得を行います。
例えば、トランジションが管理職への昇進であれば、マネジメント力やチームビルディングの知識が求められるでしょう。
会社として実施できる施策としては、役割認識を促す研修やピアラーニングの機会の設定、スキルアップに活用できる学習リソースの提供などが挙げられます。
学習リソースとしては、社内研修に加え、ALL DIFFERENTが提供するビジネススキル診断ツール「Biz SCORE」、行動計画の作成を含む各種研修といった社外リソースの活用も効果的です。
「ビジネススキル診断ツール<Biz SCORE>」の詳細はこちら
(4)必要な知識・スキルの習得や環境整備を行う
多角的な点検と新しい役割に向けた行動計画ができれば、いよいよ具体的なアクションへ進めます。
シュロスバーグの理論であれば3段階目の「転機を受け入れ、対処する」段階、ニコルソンのトランジション・サイクル・モデルであれば「順応」の段階にきたといえるでしょう。
この段階では、OJTやOff-JTを活用した計画的な支援と成功体験の積み重ねがポイントになります。仮に業務で何らかの失敗があっても、それを一方的に責めるのではなく、フィードバック面談などを利用して要因と建設的な対策を話し合いましょう。
過去の経験が妨げになっている場合は、学習棄却(アンラーニング)の実施も考慮すべきです。
アンラーニングとは、過去のノウハウや成功体験からの学び、価値観を現在の状況に照らして取捨選択し、新しい状況や役割に応じたやり方に入れ替えていくことを指します。
(5)安定化を目指して実践を継続し、振り返り・改善を行う
最後のステップは、ニコルソンのトランジション・サイクル・モデルでいえば「安定化」の段階です。恐怖心や空虚感が落ち着き、新しい役割にも慣れてきた段階であり、「トランジションを乗り越えた段階」といってもよいでしょう。
ここで大切なのは「振り返り」と「改善」です。うまくいったことだけでなく、うまくいかなかったことにも目を向け、なぜそうなったのかを考えることで、次の行動に活かせます。
このサイクルを繰り返すことで、自分なりのスタイルや強みが定着していきます。安定期とは、「何があっても自分らしく対応できる状態」を意味するのです。
定期的なフィードバック面談では、目標の達成度や成果、業務の進め方でよかった部分を承認しましょう。改善点がある場合は、よかった点の承認を行ったあとで、要因と対策、目標の再設定を検討する進め方が有効です。
社員のトランジションを成功させる3つのポイント
職場における役割の変化や異動、ライフイベントに伴う働き方の見直しなど、社員が経験するトランジションは多岐にわたります。
こうした変化をスムーズに乗り越えるためには、企業側の支援も欠かせません。個人の努力だけに任せるのではなく、組織全体でトランジションを支援することが、社員の成長と定着率向上につながります。
最後に、社員のトランジションを成功させるために企業が取り組むべき3つのポイントを紹介します。
(1)トランジションの必要性・メリットを伝える
社員のトランジションを支える第一歩は、なぜ変化が必要なのか、どのような価値があるのかを明確に伝えることです。
VUCAの時代、課題と能力に応じた適材適所が、組織全体の生産性向上とイノベーションにつながり、生き残りの鍵となります。急激な変化に対応するには、人材の再配置も必要でしょう。
トランジションは、本人が望む場合もあれば、そうでない場合もあります。しかし、「どう向き合うか」が本人のキャリア形成に大きく影響することは変わりません。
新しい役割を認識し、必要な知識・スキルの獲得を「チャンス」と捉えて取り組めれば、会社にとってより必要な人材になり得ます。
変化に対して不安や抵抗を感じるのは自然なことですが、その背景や目的を理解すれば、納得感が生まれます。企業としては、トランジションを通じた「成長の機会」であることを丁寧に伝える姿勢が求められます。
こうしたトランジションの必要性・メリットは、人材の再配置の準備段階で広く発信していくことが大切です。同時に、
- ロールモデルとなる社員に経験を共有してもらう
- 経営層から期待することを直接話してもらう
など、具体的なエピソードや期待を伝えると、トランジションの先の姿をよりイメージしやすくなるでしょう。
(2)職場環境・業務フローをアップデートする
トランジションを成功させるためには、環境面の見直しも欠かせません。
トランジションが発生すると、従来のやり方ではうまくいかなくなる場合があります。その場合は、新しい役割や業務に適応しやすいように、業務フローやツール、チーム体制などを柔軟にアップデートしましょう。
個人単位の業務フローだけでなく、組織単位の職場環境の調整、業務フローの改善も視野に入れなければなりません。
変化に伴う混乱を最小限にとどめるためにも、物理的・制度的な環境整備を進めることが効果的です。
(3)研修やワークショップを開催してノウハウを伝える
トランジションを乗り越えるには、大きな視点での改善だけでなく、より具体的なノウハウの提供も欠かせません。トランジション期にある社員には、必要な知識やスキルを学べる機会を提供するようにしましょう。
特に、役割転換に伴うマネジメント能力やコミュニケーション力などは、現場での経験だけでなく体系的な学習が必要です。そのため、企業内で研修やワークショップを定期的に実施し、実践に役立つノウハウを提供することが求められます。
例えば、次期リーダー職や管理職に昇進・昇格予定がある社員への研修では、次期管理職研修、管理職研修、キャリア研修がおすすめです。
【キャリアトランジションに対応した研修の例】
| 研修例 | 主な内容 |
|---|---|
| 次期管理職研修 |
|
| 管理職研修 |
|
| キャリア研修 |
|
| 女性のトランジションサポートプログラム |
|
特に、妊娠・出産など女性社員が直面するトランジションは、まだ十分な理解がされているとはいえません。どのような課題があるのかを認識し、理解することが、適切な支援の第一歩となります。
ALL DIFFERENTでは、人材育成研究の第一人者である中原淳教授とともに、「女性の視点で見直す人材育成 トランジション サポート プログラム」を開発しました。多様化する女性のトランジションの理解、性別を問わず活躍できる職場作りに、ぜひお役立てください。

