パワーハラスメント(パワハラ)とは?定義と裁判例、防止措置の内容
 公開日:2025.07.02
公開日:2025.07.02
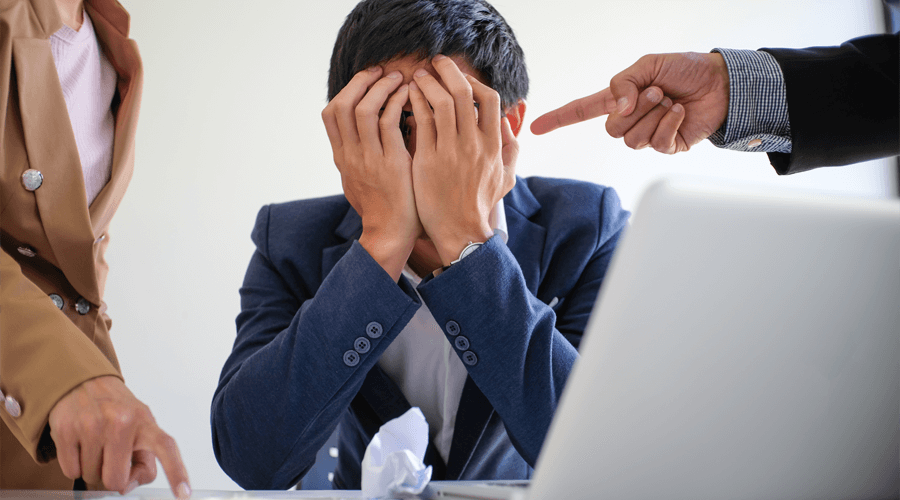
パワーハラスメント(パワハラ)とは、優越的な関係を利用して相手に不当な言動を行うこと。パワーハラスメントは職場環境の安全性を損ない、ときに従業員の心身の不調を招きます。そのため、企業にはパワーハラスメント防止に向けた取り組みが義務付けられました。
本コラムでは、厚生労働省によるパワーハラスメントの定義と6類型、裁判例、防止措置として取り得る具体的な施策を解説します。
パワーハラスメントとは?厚生労働省による定義と6類型
パワーハラスメントの定義と類型は、厚生労働省が様々な資料で紹介しています。定義には3つのポイントがあり、これが「パワーハラスメントかどうか」の基本的な判断基準となります。
パワーハラスメントの6類型とともに、まずは基本を確認していきましょう。
厚生労働省によるパワーハラスメントの定義と要件
厚生労働省は、ポータルサイト「あかるい職場応援団」やパンフレットなどで、以下のようなパワーハラスメントの定義を示しています。
【パワーハラスメントの定義】*
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすもの
パワーハラスメントの定義における3要素は、より具体的にいえば、以下のようになります。
【パワーハラスメントの3要素】*
| 要素 | 具体的には… | 例 |
|---|---|---|
| ①優越的な関係を背景としている | 行為者とその言動を受ける労働者との間に、抵抗・拒絶しにくい関係性がある |
|
| ②業務上必要かつ相当な範囲を超えている | 一般的に考えて、明らかに必要性がなかったり、やり方が正当なものとは認められなかったりする言動である |
|
| ③労働者の就業環境を害する | 従業員の心身に苦痛を与えたり、職場環境が悪化して従業員が能力を発揮しにくくなったりするような、看過できない程度の悪影響 |
|
なお、「②業務上必要かつ相当な範囲を超えている」は、1つの要素で判断することが難しく、様々な要素を総合的に考慮しなければなりません。一見パワーハラスメントに感じられる言動があっても、その言動が生じた背景や行為者側の意図、受け手側の感じ方、その言動の影響などを見ると、「少し厳しいものの、指導の範囲である」と考えられる場合もあるからです。
あくまで事実関係と「平均的な労働者の感じ方」をもとに判断することが大切です。
パワーハラスメントの6類型
定義にある3つの要素を満たせば、その言動はパワーハラスメントになります。ただ、これではまだ漠然としており、具体的なイメージはつかみにくいでしょう。そこで、基本の定義に加えて6つの類型を見ておきましょう。これらに当てはめることで、より判断しやすくなります。
パワーハラスメントの6類型とは、下表のものです。
【パワーハラスメントの6類型】*
| 類型 | 発言例・行為例 |
|---|---|
| 身体的な攻撃 |
|
| 精神的な攻撃 |
|
| 人間関係からの切り離し |
|
| 過大な要求 |
|
| 過小な要求 |
|
| 個の侵害 |
|
具体的な事例を見ると、身体的攻撃や過大/過小な要求は上司から部下、先輩社員から後輩社員といったケースが多く見られる一方で、精神的攻撃や人間関係からの切り離しは同僚間で行われるケースもあります。
「管理職だから」「一般社員だから」という職位だけでなく、職場の状況に関わる様々な観点から、パワーハラスメントの有無を判断することが大切です。
パワーハラスメントに関する実態調査
実際のところ、パワーハラスメントはどのくらい発生しているのでしょうか。
ここで、厚生労働省による「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」から、企業におけるパワーハラスメントの相談件数や発生件数、従業員におけるハラスメントを受けた経験やパワーハラスメントの内容などをご紹介します。
企業を対象とする「企業調査」と労働者を対象とする「労働者等調査」を順番に見ていきましょう。
企業調査によるパワーハラスメントの相談・発生件数と推移
まず企業調査を見ると、過去3年間についてハラスメント相談の有無において、パワーハラスメントの相談は「ある」とした企業が全体の64.2%でした。従業員規模別では、規模が大きくなるにつれて「ある」と答えた割合が大きくなり、99人以下の企業で30.0%、1,000人以上の大企業で94.4%となっています。
また、パワーハラスメントに関する相談の有無を業種別に見ると、最も「ある」の割合が大きかったのは金融業・保険業(156社)の76.9%でした。企業数が多い卸売業・小売業(1,235社)では68.9%、製造業(1,736社)では64.0%となっています。
相談件数の推移では、パワーハラスメントの場合、「増加している」と答えた企業は19.6%、「変わらない」と答えた企業は30.2%、「減少している」とする企業は21.8%でした。「わからない」と答えた企業は、全体の約3割となる28.4%でした。
他方、実際にパワーハラスメントがあったと認められる事例の有無では、パワーハラスメントの相談があった企業のうち73.0%が「該当する事案がある」と答えています。事例件数の推移では、13.4%が「増えている」、31.3%が「変わらない」、28.8%が「減少している」と答えました。「わからない」と回答した企業は、26.4%でした。
全体としては、パワーハラスメントの相談があった企業は約6割を占め、そのうち7割で、実際にパワーハラスメントが発生したと認められました。相談件数や事例件数の推移では「変わらない」「減少している」とする企業が過半数ではあるものの、「わからない」と回答した企業も約4社に1社の割合で見られました。
パワーハラスメントの状況に関する実態把握を社内でも積極的に進める必要がありそうです。
参考:「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」(厚生労働省)pp.32-52
労働者等調査から見る“ハラスメントを受けた経験”とその内容、行為者
次に、ハラスメントを受けた従業員の状況を労働者等調査から確認していきましょう。
パワーハラスメントを受けたことがある人は、全体の19.3%でした。約5人に1人が、何らかのパワーハラスメントを受けている計算です。さらに、パワーハラスメントを受けた人の3人に1人は「何度も繰り返し」、2人に1人が「時々」受けるなど、複数回経験している労働者が多いことがわかりました。
さらに、会社側のハラスメント防止に向けた取り組みに対する評価と併せて見ると、「あまり取り組んでいない」と評価された企業では、パワーハラスメントを経験した人の割合が多くなり、「積極的に取り組んでいる」企業の約2.3倍になりました。あまり取り組んでいない企業では、パワーハラスメントを受けた経験のある人は35.1%。これに対し、積極的に取り組んでいる企業では15.3%です。
受けたパワーハラスメントの内容、行為者のトップ3は、以下の通りです。
【パワーハラスメントの内容(複数回答・上位3つ)】*1
| 内容 | 割合 | |
|---|---|---|
| 1位 | 精神的な攻撃 (脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言) |
48.5% |
| 2位 | 過大な要求 (業務上明らかに不要なことの強制、遂行不可能なことの強制、仕事の妨害) |
38.8% |
| 3位 | 人間関係からの切り離し (隔離・仲間外し・無視) |
27.8% |
【パワーハラスメントの行為者(複数回答・上位3つ)】*2
| 行為者 | 割合 | |
|---|---|---|
| 1位 | 上司(役員以外) | 65.7% |
| 2位 | 会社の幹部(役員) | 24.7% |
| 3位 | 同僚 | 20.2% |
全体として、上司や役員など職位が上の人からパワーハラスメントを受けた人が6割以上を占め、内容としては精神的な攻撃や過大な要求が目立ちます。
こうしたパワーハラスメントを受けた人に生じた心身への影響で多く選ばれたものは、以下の3つでした。
【パワーハラスメントによる心身への影響(複数回答・上位3つ)】*3
| 内容 | 割合 | |
|---|---|---|
| 1位 | 怒りや不満、不安などを感じた | 68.5% |
| 2位 | 仕事に対する意欲が減退した | 61.1% |
| 3位 | 職場でのコミュニケーションが減った | 36.3% |
パワーハラスメントを受けた従業員は、ひどく嫌な思いをするとともに、仕事へのモチベーションが減少し、人間関係にも影響が出ているようです。こうした状況では、本来の能力を発揮できません。
企業調査では、パワーハラスメントの件数は「減少している」という企業の割合が「増えている」を上回っていましたが、「わからない」と回答した企業も多く見られます。改めてそれぞれの企業が自社の状況を正確に把握し、取り組みを強化していくことが、安心・安全な職場づくりには欠かせません。
パワーハラスメントの実例と裁判例
パワーハラスメント防止措置義務には罰則がないため、防止措置を講じていなかったり、パワーハラスメントの発生自体を理由として懲役や罰金などの処罰を受けるわけではありません。
ただ、労働施策総合推進法第33条第2項により、パワーハラスメントの防止対策に大きな問題がある企業については厚生労働大臣による助言・指導・勧告が行われる場合があり、それでも改善されない場合は企業名が公表される恐れがあります。
また、パワーハラスメントの内容・やり方によっては、損害賠償責任が行為者や企業に生じる場合もあります。
では、具体的にどのような裁判例があるのでしょうか。厚生労働省のポータルサイト「あかるい職場応援団」に掲載されている事例から、いくつか見ていきましょう。
「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」の裁判例
「身体的攻撃」「精神的な攻撃」の裁判例には、従業員Aさんが役員2名から日常的な暴行や退職勧奨を受けており、それを原因として自殺に至ってしまった事例があります。従業員の遺族が会社と会社役員2名を訴えました。
この事案で裁判所によって認定された事実は、以下のものです。
【パワーハラスメントの内容】*
- ①Aさんが仕事でミスをした際、「てめえ、何やってんだ」「ばかやろう」などと大声で怒鳴り、頭を叩く・殴る、蹴るなどしたことが複数回あった
- ②Aさんのミスで会社に生じた損害について弁償するよう求め、弁償しないなら家族に支払ってもらうと述べた
- ③Aさんに対して「会社を辞めたければ7,000万円払え。払わないと辞めさせない」と述べた
- ④Aさんの大腿部後面を2回蹴り、全治12日間の両大腿部挫傷を負わせた(自殺の7日前に発生)
- ⑤Aさんに対して退職届を書くよう強要し、Aさんが書いた下書きには「会社に利益を上げるどころか、逆に余分な出費を重ねてしまい迷惑をお掛けしたことを深く反省し、一族で誠意をもって返さいします。二ヶ月以内に返さいします」と記載されていた。また、「額は一千万〜一億」と鉛筆で書かれ、消された跡があった(自殺の3日前に発生)
上記のうち、①と④が身体的攻撃に当たります。それ以外の暴言や強要などは精神的攻撃です。
裁判所は、こうした事実から、被告会社と役員1名に対して、合計5,400万円余りの損害賠償を命じました。これには、死亡したAさんが生きていたら得られたであろう収入相当額と慰謝料などが含まれています。
①と④のような行為は刑法における暴行罪に該当し、不法行為で損害が発生した場合は損害賠償責任が発生し得ます(民法709条)。また、暴言は精神的攻撃に当たり、特に大声や厳しすぎる言葉は不法行為と認められやすいでしょう。
行為者自身は「指導」のつもりでも、それがエスカレートし、本来必要のない「嫌がらせ」に発展してしまうことがあります。特に殴る・蹴るといった行為は、指導・教育という名目であっても認められるものではありません。
*参考:「【第22回】パワハラ、暴行等と自殺との間に相当因果関係有りとして高額の損害賠償」(あかるい職場応援団)
「人間関係からの切り離し」の裁判例
「人間関係からの切り離し」は、精神的攻撃とともに行われるケースが多く見られます。今回ご紹介する裁判例も、“新入社員を近づけない”といった切り離しが行われる前に、社内会議で罵倒されるなどの精神攻撃が生じています。
その事案では、高額商品の販売を行っていた会社の正社員であるDさんが、セールストークのマニュアルに法的に許されない医療的効能の説明があるとして、上司に質問したり顧客からの解約に応じていたりしたことで、社内でいじめや退職の強要をされました。一連の行為を受け、Dさんは腰を痛めるとともに、うつ状態に陥りました。
【パワーハラスメントの内容】*
- ①Dさんは顧客から解約したい旨のクレームを受けて上司Eさんに相談し、Eさんの指示で顧客に解約を伝えた。しかし、社内会議で専務Fさんから強く非難され、「営業成績が悪く、解約が多いのに、サプリメントアドバイザーを名乗っているとみんな笑っている」などと罵倒された
- ②Dさんは社内で常時監視される状態に置かれ、Dさんに新人を近づけさせない、あいさつをしても返さないといった人間関係の切り離しが行われた
- ③正社員であるDさんに、主にパートやアルバイトの従業員が担当しているテレフォンアポインターへ異動させる命令が出された。これを「降格である」と解釈したDさんが拒否すると、専務FさんがDさんに電話をかけ、大声で「あなたがいると会社がつぶれてしまう。言うことを聞かなければ自宅待機だ」と強く言った
- ④上司Eさんが、専務Fさんの指示により、全ての私物を持って会社から退去するようDさんに伝えた
- ⑤Dさんは、私物を持って退去する際に、重い荷物のために激しい腰痛となり、その後うつ状態にも陥った
- ⑥腰痛で動けなくなっていたDさんの自宅に会社の総括部長が電話をかけたり自宅訪問をしたりして、出社できないのであれば退職届を出すよう求めた
裁判所は、被告会社の専務Fさんや上司Eさんらの行為が不法行為であり、Dさんのうつ状態などの傷害の原因となったことから、損害賠償責任を認めました。
本来であれば、Dさんをいじめによって退職に追いやるのではなく、丁寧な説明と話し合いによってDさんの理解を得られるよう努めたり、法令に違反するという指摘を受けて営業方法を再検討したりすることが、望ましい対応となります。
適切な対応を行わず、嫌がらせによる排除を続ければ、会社全体のモラルや秩序に深刻な影響を与えてしまいかねません。そうした意味でも、パワーハラスメントは建設的な問題解決策からはほど遠い手段であることがわかります。
*参考:「【第53回】罵倒、のけ者にするなどといった行為が不法行為にあたると判断された事案」(あかるい職場応援団)
「過大な要求」「過小な要求」の裁判例
従業員の能力と比べて負担が大きすぎる業務(過大な要求)や負担が少なすぎる業務(過小な要求)を意図的に割り当てることも、パワーハラスメントに認定される場合があります。
裁判例としてご紹介するのは、旅行事業部をもつ企業での事案です。旅行事業部の経理担当となったGさんが、上司Hさんの指示のもとで、根拠不明の出金などの調査を行ったところ、他の従業員数名が反発して嫌がらせが始まりました。
【パワーハラスメントの内容】*
- ①上司Hさんが添乗業務でニューヨーク市に滞在した同時期に、Gさんも旅行でニューヨーク市に滞在したところ、社内で2人が「男女関係にある」とする噂が広まった。Gさんは専務Iさんと社長Jさんに事実ではないことを述べて改善を求めたものの、何ら対応されなかった
- ②旅行事業部を分割する組織変更によってGさんは経理担当を外され、物産展業務に1人で従事することになった。物産展業務は早朝から深夜に及ぶ勤務であり、休憩も取れず、土日出勤もあった
- ③Gさんは専務Iさんと社長Jさんに人員補充を求めたが、特段の措置は取られなかった。一方で、他の部員はあまり残業せずに帰宅していた
- ④元上司Hさんが解雇され、新しい上司Kさんが就任し、Gさんは上司Kさんから内勤業務を命じられた。しかし、ほとんど仕事を与えられない状況が続いた
- ⑤Gさんが休暇を申請したところ、行き先などを示すホワイトボードに「永久に欠勤」などと記載されたり、Gさんの名前が消されたりした
- ⑥会社が整理解雇を行う際、会社側は希望した従業員に再就職あっせんを行い、再雇用先を確保した。しかし、Gさんに対しては希望の有無すら問わず、ほかの従業員よりも先に解雇した
上記において②と③が過大な要求、④が過小な要求となります。
裁判所は、社内での様々な嫌がらせがGさんの入社から解雇まで1年余りにわたって繰り返されていたことを知りながら、何ら防止措置を執らなかったとして専務Iさんと社長Jさんの責任を認めています。
加えて、嫌がらせの一部が業務命令として行われていた事実から、これらが専務Iさんおよび社長Jさんの指示または了解のもとで行われていたとし、民法709条の不法行為の責任があるとしました。
判決は、代表取締役個人および会社が連帯して損害賠償責任を負うものとして、Gさんの受けた精神的苦痛に対する慰謝料150万円、Gさんが欠勤を余儀なくされた日に対する休業損害を、不法行為と相当因果関係のある損害として忍容しています。
このように、嫌がらせとして1人部署に配属し、過大または過小な要求を行った場合は、パワーハラスメントに該当する可能性が高くなります。
*参考:「【第38回】一連の行為が、労働者を孤立させ退職させるための"嫌がらせ"と判断され、代表取締役個人及び会社の責任が認められた事案」(あかるい職場応援団)
パワーハラスメント防止措置における対策例
パワーハラスメント防止措置は全ての企業に義務付けられていますが、具体的にどのような取り組みを行えばいいのでしょうか。これを解説した公的なマニュアルが、厚生労働省による「パワーハラスメント対策導入マニュアル」です。2025年2月現在、第4版となっています。
対策の大きな流れは、以下のような構成です。
【パワーハラスメント防止措置の流れ】
- トップからのメッセージ発信
- 就業規則への規定と相談窓口の設置・周知
- パワーハラスメント研修
- 現場の実態把握や日々の声かけ
- パワーハラスメントへの対応
- 再発防止に向けた取り組み
同マニュアルから、防止措置の主なポイントをピックアップしてご紹介します。
トップからのメッセージ発信
まず行うべきことは、社長など会社の経営層がパワーハラスメントについての理解を深め、そのトップから「パワーハラスメントは許さない」というメッセージを全従業員に向けて発信することです。
啓発や周知というと、パンフレットを配布したりポスターを掲示したりするだけで終わっている組織もあるかもしれません。しかし、それだけでは従業員にとって“他人事”のままになる恐れがあります。
トップの声で、現場のメンバーにも届くように訴えかけることが、パワーハラスメントのない企業風土の醸成において最も重要なポイントです。
就業規則への規定と相談窓口の設置・周知
経営層のパワーハラスメント研修と同時に、会社におけるルール化と体制整備を進めましょう。具体的には、就業規則への規定と相談窓口の設置です。
就業規則への規定としては、厚生労働省によるマニュアルの20ページに例があります。
例えば、「職場のパワーハラスメントの禁止」という項目を追加するとともに、懲戒規定における懲戒事由の中に、パワーハラスメント禁止への違反を追加するなどです。就業規則本体に「パワーハラスメントの禁止」という項目を追加し、「詳細は『パワーハラスメントの防止に関する規定』により別に定める」として、新たに規定を作成する方法もあります。
また、より効果的な施策とするには、事前に労働組合や労働者の過半数代表者と話し合い、「パワーハラスメント防止に関する協定書」を作成するとよいでしょう。
協定書には、
- パワーハラスメントの定義
- パワーハラスメントを禁止すること
- 相談・苦情への対応
- 相談や苦情を申し出た従業員への不利益取り扱い禁止
などを定めます。
相談窓口については、社内に設置する方法と社外に委託する方法があります。
先述の実態調査によれば、ハラスメント相談窓口を社内のみに設置している企業は中小企業でより多く見られ(従業員数99人以下の企業で73.4%)、大企業では38.2%でした。他方、社内と社外の両方に設置している企業の割合は従業員数が増えるほど大きくなり、大企業では59.7%が両方に設置していると回答しています。*1
従業員にとっての相談のしやすさを考えれば、社内の窓口とともに、社外の窓口も利用できるとよいでしょう。
メッセージの発信方法や相談窓口の周知に関する施策では、会社ごとに多様な方法が見られます。例えば、以下のような方法で周知が行われていました。*2
- 全体朝礼で社長から説明する
- 社内に掲示するとともにイントラネットに掲載し、いつでも確認できるようにする
- 相談窓口の案内をカードで全員に配布する
従業員がいつでも相談先を確認し、活用できるよう、現場に合う方法を検討しましょう。
*1 出典:「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」(厚生労働省)p.78、図表74
*2 出典:「他の企業はどうしてる?」(あかるい職場応援団)
パワーハラスメント研修
経営層によるパワーハラスメント防止への理解・メッセージ発信とルール化を実施したら、次は全従業員の理解促進と意識付けです。研修では、パワーハラスメントは何か、なぜパワーハラスメントをしてはならないのかといった基本を伝えましょう。
ただ、最初から「パワーハラスメントはダメです」と伝えるだけでは、一方的に怒られている印象を抱かせてしまうかもしれません。これを避けるには、「会社として従業員を守るために、パワーハラスメント防止措置を実施する」というメッセージが伝わるよう、プログラムを工夫するとよいでしょう。
ある企業では、最初にメンタルヘルス研修を実施し、従業員の心身の健康を大切にすることを理解してもらったうえで、セクハラ・パワハラ防止研修を行いました。管理職への研修を実施したあとにアンケートを実施し、自らの行動に対する意識を高め、対策の必要性に気づく機会とした企業もあります。
ハラスメントに関する研修は、パワーハラスメント単独で実施することもできますし、ほかのハラスメントと組み合わせて伝えることも可能です。ほかのハラスメントについては、以下の関連コラムで解説しています。研修プログラムや施策の立案にぜひご活用ください。
コラム「ハラスメントとは?定義・種類・原因・対策を簡単にわかりやすく解説」はこちら
現場の実態把握や日々の声かけ
厚生労働省のマニュアルでは、現場の実態把握を推奨しています。ただ理念を掲げるだけでなく、現場で実践されているかどうかを定期的にチェックし、必要に応じてルールや施策を見直すためです。
実態把握で採用されている方法は、主にアンケートや日常的な現場の確認。従業員アンケートでは、ハラスメントを受けたり、見聞きしたりしたことがないか、その内容や行為者について匿名で記入してもらいます。自由記述欄を設けている会社も複数見られました。
現場の確認は、ハラスメントの有無にかかわらず、日頃から巡回し、働きやすい職場の雰囲気になっているかどうかを確認するものです。社長自ら出向く会社もあれば、ハラスメント防止委員会の委員長などが巡回する会社もあります。
多角的な視点から現場の状況を確認し、課題が見つかった場合は早期解決を図ることで、パワーハラスメントを未然に防げるでしょう。
パワーハラスメントへの対応
もしパワーハラスメントが職場で発生してしまった場合は、相談者やハラスメント受けた従業員の話を丁寧に聴き、必要に応じて第三者にもヒアリングしつつ事実確認を進めることが大切です。
特に注意しなければならないのは、相談窓口の担当者が相談者からの話を急かしたり、行為者と疑われる従業員や相談者の一方の立場だけを重視して判断したりしないようにすることです。
可能な限り中立の立場で相談・苦情に応じ、事実確認ができたら、具体的な措置を検討しましょう。パワーハラスメントの事案が認められた場合に取り得る行為者への措置には、以下のものがあります。
【ハラスメント行為者への措置(例)】*
| 措置の例 | 具体例 |
|---|---|
| 行為者への注意・指導 |
|
| 行為者から相談者への謝罪 |
|
| 配置転換 |
|
| 行為者への懲戒処分 |
|
| 上長による見守りと声かけ |
|
これに対し、相談者には心身の健康に配慮した適切なフォローが必要です。具体的には、以下のような方法があります。
【相談者へのフォロー(例)】*
| フォローの例 | 具体例 |
|---|---|
| 状況説明 |
|
| 相談者自身の言動への助言 |
|
| 配置転換 |
|
| メンタルケアのサポート |
|
対応に迷う場合は、顧問弁護士や社会保険労務士、労働局の総合労働相談コーナーに相談するという選択肢もあります。
*参考:「パワーハラスメント対策導入マニュアル 第4版」(厚生労働省)pp.36-45
再発防止に向けた取り組み
パワーハラスメント防止措置は、ルール化と窓口設置、発生した事案への対応だけで終わりではありません。パワーハラスメントの再発防止に向けて、現在の施策の効果を検証し、改善していくことが求められます。
検討を進める際は、ぜひ実際に発生した事案を役立てましょう。例えば、次のような視点が役立ちます。
【再発防止に向けた施策検討の観点(例)】*
- その後の職場環境は、相談者にとって安全で快適になっているか?
- 行為者が同様の問題を起こす恐れはないか?
- 新たな行為者が発生する職場環境になっていないか?
- パワーハラスメントに該当する事案の発生時に、管理職に注意喚起をしているか?
- 各事案の原因と対策について、社内ルールや研修、トップからのメッセージに反映させるべきポイントは何か?
パワーハラスメントの原因と対策に関する研修には、直接ハラスメントをテーマとする研修以外にも、原因の解決・軽減につながる「アンガーマネジメント研修」や「コミュニケーションスキル向上研修」「タイムマネジメント研修」といったプログラムも有効です。
パワーハラスメント防止は、正しい理解から
パワーハラスメント防止措置が企業に義務付けられ、「パワーハラスメントとは何か」「なぜダメなのか」といった理解が進んできました。とはいえ、普段から厳しい言葉を使う傾向のある従業員や、適切なコミュニケーション方法が取られていないケースでは、知らないうちにパワーハラスメントに発展してしまうことがあるかもしれません。
パワーハラスメントを防ぐには、具体的な課題が発生した際にどのように対応すればよいのかを、まずは経営層や管理職から理解していく必要があります。
多くの企業で人材育成に伴走してきたALL DIFFERENTでは、様々な階層を対象とする研修を多数ご用意しています。働きやすい職場づくりとパワーハラスメント防止に、ぜひご活用ください。
「【管理職向け】労務管理研修<セクハラ・パワハラの基礎知識編>」の詳細はこちら
「伝え方研修~相手に理解・納得してもらうための伝え方~」の詳細はこちら
このほか、企業の課題や対象者に応じて研修プログラムを作成・実施する講師派遣型研修もご提供しています。ハラスメントのない企業風土の醸成などもサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

