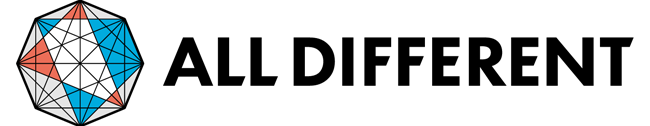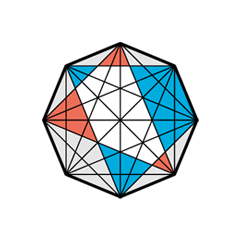フレックスタイム制とは?コアタイム・残業・メリット・デメリット
 更新日:2026.01.14
更新日:2026.01.14
 公開日:2024.01.15
公開日:2024.01.15

フレックスタイム制は、従業員が一定の範囲で始業・終業時刻を自由に決められる柔軟性のある勤務制度です。多様な働き方の実現に大きく貢献する制度である一方、勤怠管理は複雑になります。
本コラムでは、フレックスタイム制の基本的な仕組みと用語、裁量労働制などとの違い、導入のメリット・デメリットや残業時間の取扱い、実際に導入する際に必要な労使協定・就業規則、導入の流れまで、わかりやすく解説します。
フレックスタイム制とは何か?導入目的と基本の仕組み
はじめに、フレックスタイム制の仕組みと一般的な導入目的を簡単に見ていきましょう。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、一定期間の労働時間の合計を決めておき、各日の始業時刻・終業時刻・労働時間は原則として従業員自身が決められる制度のことです。次のような特徴があります。
【フレックスタイム制の特徴】
- あらかじめ定められた一定期間の労働時間の枠内で働く
- 1日の労働時間帯を固定しない
- 従業員が始業時刻・終業時刻を自由に決められる
「フレックス制」や「フレックス勤務」など、いくつかの呼び方がありますが、いずれも同じ仕組みを意味します。
フレックスタイム制の導入目的
フレックスタイム制は、多様な働き方を実現する1つの手段として導入されています。
例えば、以下のようなケースについて、従来の働き方では遅刻・早退が発生したり、そもそも会社側がそうした働き方を認めなかったりしました。フレックスタイム制では、これらの働き方も“通常の働き方”に含まれることが多く、遅刻・早退の手続きも不要です。
【フレックスタイム制による柔軟な働き方の例】
- 通院日は、午後1時から6時間だけ働く
- 通勤ラッシュを避けたいので、午前11時から8時間働く
- 子どもの学校の行事がある日なので、午後1時に退勤する
一人ひとりが仕事とプライベートのバランスを取りながら、無理のない働き方を実現できる点が、フレックスタイム制の大きな魅力。通勤ラッシュで体力を消耗しやすい人や定期的な通院が発生する人にとっても、体調を管理しやすい仕組みとなっています。
フレックスタイム制の「コアタイム」と「スーパーフレックスタイム制」
多くの場合、フレックスタイム制では「コアタイム」と「フレキシブルタイム」という2種類の時間帯が設定されます。それぞれ下表のような時間です。
【フレックスタイム制のコアタイム・フレキシブルタイム】
| コアタイム | 全従業員が必ず勤務しなければならない時間帯 |
|---|---|
| フレキシブルタイム | コアタイム以外の時間帯で、従業員が自分で始業時刻・終業時刻を決められる時間帯 |
コアタイムの設定は必須ではなく、コアタイムなしのフレックスタイム制もあります。これは「スーパーフレックスタイム制」や「フルフレックス」などと呼ばれます。
フレックスタイム制と裁量労働制・変形労働時間制・時差出勤の違い
フレックスタイム制を理解するには、裁量労働制や変形労働時間制、時差出勤との違いも確認しておくと役に立ちます。
フレックスタイム制と裁量労働制の違い
裁量労働制とは、実際の労働時間に関係なく事前に定めた労働時間(みなし労働時間)で管理する制度です。「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」があり、それぞれ対象となる業務が定められています。そのため、どのような職種についても適用できるわけではありません。
【裁量労働制が適用できる業務】
| 分類 | 対象業務 |
|---|---|
| 専門業務型裁量労働制 |
|
| 企画業務型裁量労働制 |
以下の要件を全て満たす業務
|
フレックスタイム制との違いは、対象業務の制限の有無と残業時間の扱いです。フレックスタイム制では対象業務に制限はなく、残業時間は主に「法定労働時間の総枠」を超えた労働時間で計算されます。
他方、裁量労働制では、対象業務が制限されており、残業代は原則として発生しません。これは、実際に働いた時間ではなく「みなし労働時間」をもとに賃金を計算するからです。
フレックスタイム制と変形労働時間制の違い
変形労働時間制は、業務の繁閑や特殊性に応じて、従業員の労働時間を柔軟に調整できる制度です。例えば、繁忙期の所定労働時間を通常より長く設定し、閑散期の所定労働時間は通常より短く設定するなどの運用ができます。
フレックスタイム制度は、変形労働時間制の1つです。厚生労働省の「就労条件総合調査」でも、変形労働時間制の下位分類に位置づけられています。*1
ただし、同じ厚生労働省の調査でも、2025年3月に公表された「労働時間制度等に関する実態調査」では、従来の変形労働時間制とは独立にフレックスタイム制を定義しました。*2
フレックスタイム制とその他の変形労働時間制の違いは、従業員自身が始業時刻・終業時刻・労働時間を決められるか否かにあります。フレックスタイム制以外の変形労働時間制では、会社が日々の始業時刻・終業時刻・労働時間を定め、従業員に選択の余地はありません。
*1 参考:「令和6年就労条件総合調査 結果の概況(労働時間制度)」(厚生労働省)
*2 参考:「労働時間制度等に関する実態調査 / 調査の説明」(e-Stat)
フレックスタイム制と時差出勤の違い
時差出勤とは、従業員が働く時間帯を選択できる制度です。主に通勤ラッシュを避ける目的で活用されますが、家庭生活で忙しい時間帯をプライベートに充てるために活用されることもあります。
時差出勤とフレックスタイム制の大きな違いは、1日の労働時間を従業員が決められるか否かです。
時差出勤では、働く時間帯が前後にずれるだけで、1日の労働時間は会社が定めた通りに働かなければなりません。例えば、1日の所定労働時間が7時間(+休憩1時間)なら、「午前9時から午後5時まで働く」「午前11時間から午後7時まで働く」といった形になります。
これに対し、フレックスタイム制では始業時刻・終業時刻、そして1日の労働時間も自ら決めることができます。「朝9時から5時間だけ働く」「朝11時から9時間働く」など、時差出勤よりも柔軟性のある働き方ができるのです。
フレックスタイム制の清算期間・総労働時間・標準となる1日の労働時間と有給休暇
では、フレックスタイム制の詳しい仕組みを見ていきましょう。必須用語は「清算期間」「総労働時間」「標準となる1日の労働時間」です。
「清算期間」とは
清算期間とは、フレックスタイム制における労働時間を管理する一定の期間のことです。最大3カ月まで設定できますが、賃金の計算期間に合わせて清算期間を1カ月とする企業が多いようです。
例えば、清算期間が1カ月であり、毎月26日を起算日(清算期間の開始日)とする場合は、26日から翌月25日までが清算期間となります。
「総労働時間」とは
フレックスタイム制での総労働時間とは、清算期間内で従業員が働くべき時間の合計のことです。総労働時間は法定労働時間を超えないよう、以下の不等式を満たすようにします。
【清算期間における総労働時間の計算式】
清算期間における総労働時間≦(清算期間の暦日数÷7)×1週間の法定労働時間
例えば、多くの企業に適用される法定労働時間「週40時間」の場合、総労働時間の上限は、清算期間が31日なら177.1時間、30日なら171.4時間となります。
保健衛生業や接客娯楽業、常時10人未満の労働者を使用する商業のような「特例措置対象事業場」の場合は法定労働時間が「週44時間」となるため、総労働時間の上限はそれぞれ194.8時間、188.5時間です。
この総労働時間の上限は「法定労働時間の総枠」と呼ばれます。
【清算期間における法定労働時間の総枠(総労働時間の上限)】
| 清算期間の暦日数 | 法定労働時間週40時間の場合 | 法定労働時間週44時間の場合 |
|---|---|---|
| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |
| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |
なお、法改正により、完全週休2日制のフレックスタイム制では「清算期間内の所定労働日数×8時間」を総労働時間の上限とすることができるようになりました。*
フレックスタイム制の対象となる従業員は、上記の範囲内で設定された総労働時間を満たすように、日々の労働時間を自己管理しながら働くことになります。
*参考:「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(2023年2月版)」(厚生労働省)p.8
「標準となる1日の労働時間」と有給休暇の賃金計算
もう1つ、賃金計算のうえで重要な用語があります。「標準となる1日の労働時間」です。従業員が有給休暇を取得した際の賃金計算に使います。
【標準となる1日の労働時間の算出方法】
標準となる1日の労働時間=総労働時間÷清算期間における所定労働日数
フレックスタイム制では、1日あたりの労働時間が固定されていません。そのため、有給休暇取得の賃金計算に使う労働時間数をあらかじめ定めておくのです。
なお、これはあくまで有給休暇のための労働時間数です。「フレックスタイム制でも1日に〇時間働かなければならない」という規定ではありませんので、ご注意ください。
フレックスタイム制の残業時間と残業代、深夜労働・休日出勤の割増賃金
フレックスタイム制では日々の労働時間を従業員自身が決められるため、1日5時間しか働かない日も遅刻・早退にはなりませんし、1日9時間働いても即座に残業扱いになるわけではありません。
しかし、一定の時間数を超えたり、本来休日であるべき日に労働をしたりすれば残業や休日労働となり、割増賃金の支払いが発生します。
残業時間・残業代の計算方法
フレックスタイム制の残業時間は、原則として法定労働時間の総枠を超えた労働時間となります。完全週休2日制の場合は「清算期間内の所定労働日数×8時間」を超えた労働時間を残業時間として計算する方式も認められています。
ここで気をつけたいのは、清算期間が1カ月を超えるケースです。1カ月以内であれば、法定労働時間の総枠を基準に計算するだけでよいのですが、1カ月超の清算期間を採用する場合、下表にように2段階で労働時間を算出しなければなりません。
【清算期間が1カ月超である場合の残業時間の計算方法】
| ステップ | 基本の計算方法 | 具体例(清算期間の暦日数91日の場合) |
|---|---|---|
| 1 | 1カ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間を算出し、残業時間とする | 1カ月=30日の例:
|
| 2 | 清算期間経過後、法定労働時間の総枠を超えた労働時間を算出し、残業時間とする(ステップ1で算出した残業時間は除く) |
|
こうした2段階の残業時間の計算が必要となるのは、清算期間が1カ月を超える場合に無理な働き方が生じないよう、「1カ月ごとに週平均労働時間50時間を超えて労働させてはならない」という定めがあるからです。
残業代は、以上の計算によって算出された残業時間に対して、割増賃金率25%以上を加えて計算します。これは、フレックスタイム制以外の残業代と同様です。
残業に関する一般的なルールは、以下の関連コラムで解説しています。
コラム「残業時間の定義は?36協定・過労死ライン・削減アイデア」はこちら
コラム「サービス残業は自主的行為でも違法!企業の法的責任と防止策」はこちら
参考:「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き (2023年2月版)」(厚生労働省)pp.14-16
深夜労働と休日労働の割増賃金
また、深夜労働や休日労働に関しても、通常同様に割増賃金が発生します。具体的な規定と割増賃金率は、下表の通りです。
【深夜労働と休日労働の規定と割増賃金率】
| 規定 | 割増賃金率 | |
|---|---|---|
| 深夜労働 | 午後10時から午前5時の時間帯に労働した場合、深夜労働となり、割増賃金の支払いが発生する | 25%以上 |
| 休日労働 | 法定休日に労働した場合、休日労働となり、割増賃金の支払いが発生する | 35%以上 |
フレックスタイム制は従業員が始業時刻・終業時刻を選べますが、その労働時間が午後10時から午前5時の時間帯に及ぶ場合は深夜労働となります。例えば、午後6時から仕事を始めて午前2時に終えた場合、午後10時から午前2時の4時間は深夜労働になるということです。
休日労働は、1週間に1日または4週に4日の法定休日に労働するケースが該当します。清算期間における総労働時間や残業時間とは別枠で計算します。割増賃金率は、最低35%です。
フレックスタイム制の4つのメリット
このように、フレックスタイム制の労働時間の管理は従来の方法と大きく異なります。それでもなおフレックスタイム制の導入が注目されているのは、やはり多様な働き方の実現への期待が大きいからでしょう。
多様な働き方が実現されれば、従業員側にも会社側にも以下のようなメリットが生まれます。
- (1)ワークライフバランスとエンゲージメントの向上につながる
- (2)無駄なく働き、生産性向上につながる
- (3)人材確保と離職防止の効果を見込める
- (4) 残業代の支払いを減らせる可能性がある
順番に解説します。
(1)ワークライフバランスとエンゲージメントの向上につながる
フレックスタイム制を導入すると、従業員は自身の都合に合わせて働けるようになります。家庭生活や勉強、健康管理などの時間を確保できるため、本人にとって望ましいワークライフバランスの実現が容易になるでしょう。
こうした働きやすい仕組みは、従業員の仕事に対するモチベーションや会社への信頼感を向上させます。ひいては、従業員のエンゲージメント向上にもつながります。
コラム「ワークエンゲージメントとは?3つの構成要素・測定方法・高める方法」はこちら
(2)無駄なく働き、生産性向上につながる
フレックスタイム制の導入は、効率よく働きたい人材にとっても魅力的な仕組みです。集中力が高まりやすい時間帯を中心に、始業時刻・終業時刻を決められるからです。
例えば、朝に強い人なら早めに始業して午前中の労働時間を増やし、業務効率を上げられます。午後の集中力のほうが高い人なら、始業時刻・終業時刻を遅くすることで夕方以降の労働時間をしっかり確保できるでしょう。
個々の特性に合わせてメリハリをつけ、一人ひとりの業務効率の向上は、組織全体の生産性向上にもつながります。
(3)離職防止と人材確保の効果を見込める
さらに、フレックスタイム制は離職防止と人材確保にも効果を発揮します。
勤務時間を動かせない働き方の場合、育児・介護を担っている従業員は、頻繁に遅刻・早退・欠勤をせざるを得ません。全員が同じ時間で働く中で肩身の狭い思いをするケースが多く、人間関係が悪化する恐れもあるでしょう。自身の体調が安定しない人や疲れやすい人も、ほかの人と同じ働き方をするために、無理な働き方を余儀なくされます。
「令和4年就業構造基本調査」では、過去5年以内に離職した理由に「労働条件が悪かったため」「病気・高齢のため」をあげる人が多いことがわかりました。過去1年以内に離職した人についても、介護・看護を理由とする人は10万人以上、出産・育児を理由とする人は14万人以上います。*
フレックスタイム制による柔軟な働き方の実現は、こうした人材にとって大変重要であり、働き続けるための重要な施策なのです。
*参考「令和4年就業構造基本調査」(総務省統計局)pp.26-28
(4)残業代の支払いを減らせる可能性がある
フレックスタイム制は、人件費の面でもメリットがあります。業務が多い日に多く働いても、清算期間における法定労働時間の総枠の範囲内であれば、残業時間が発生しないからです。
画一的な労働時間で働く場合、「1日8時間」と定めれば、その日の業務量にかかわらず8時間分の賃金が発生します。業務の少ない日に「仕事が終わっているのに退勤できず、何となく時間をつぶす」という状況であっても、8時間分の賃金です。他方、業務が多い日は8時間を超えて働くことになり、会社側は残業代を払わなければなりません。
これに対してフレックスタイム制では、業務の少ない日は早めに退勤できるため、「業務がない時間」に対する賃金を払う必要がなくなります。業務が多い日も、清算期間あたりの法定労働時間の総枠に収まる範囲であれば、残業と見なす必要はありません。
従来のような1日ごとの残業時間が発生せず、一定期間の枠内で算出すればよいフレックスタイム制では、従来よりも残業代の支払いを減らせる可能性があるのです。
フレックスタイム制はなぜ普及しない?3つのデメリット・落とし穴と対策
こうしたメリットがあるものの、フレックスタイム制の導入率は近年伸び悩んでいます。
フレックスタイム制に見られるデメリットは、メリットに潜む落とし穴ともいえます。事前にこれらのデメリットを認識し、対策を講じることが大切です。
(1)労務管理方法が変わり、一人ひとりのタイムマネジメントスキルが重要になる
1つ目のデメリットは、従来とは異なる労務管理方法となることです。特に勤怠管理が複雑になります。
フレックスタイム制では、従業員ごとに始業時刻・終業時刻・労働時間が日々変化します。しかも、残業や総労働時間に対する不足時間が発生したか否かは、清算期間経過後でなければわかりません。
フレックスタイム制の導入による勤怠管理の混乱を防ぐには、清算期間ごとの労働時間を正確に記録・確認できる勤怠管理システムの導入が必要です。労務管理を行う部署や担当者だけでなく、従業員本人も日々の労働時間をきちんと把握できるシステムがよいでしょう。
同時に、総労働時間に対する実働労働時間の大きな過不足が発生しないよう、一人ひとりのタイムマネジメントスキルの向上も欠かせません。
コラム「タイムマネジメントとは?時間を味方につける能力向上のコツと実践手順」はこちら
(2)始業時刻・終業時刻は強制できない
2つ目のデメリットは、一人ひとりの始業時刻・終業時刻を会社側から原則として指定できないことです。
フレックスタイム制の最も重要なポイントは、始業時刻・終業時刻・労働時間を従業員が自ら決められること。会社側から「必ず〇時に始業しなければならない」「必ず〇時まで働かなければならない」といった強制を行うと、フレックスタイム制の趣旨から外れてしまい、労働基準監督署から指導を受ける恐れがあります。
また、コアタイム以外の時間帯(フレキシブルタイム)について業務命令を行うことも、フレックスタイム制の趣旨に反するものとして扱われる可能性があります。
とはいえ、フレキシブルタイムに会議や商談が入ったり、顧客対応が発生したりする可能性は排除できません。そのようなケースでは、業務上必要なものとして、従業員本人の同意を得たうえで、時間を確保してもらいましょう。
参考:「効率的な働き方に向けて フレックスタイム制の導入 (6)Q&A」(厚生労働省)
(3)社内外のコミュニケーション機会が減る恐れがある
3つ目のデメリットは、誰が勤務しているのかがわかりにくくなることです。これにより、社内外のコミュニケーション不全が発生する可能性が高まります。
例えば、管理職が業務の進捗を確認したくても、「業務を担当している部下がまだ来ていない」という事態があり得ます。取引先から連絡を受けた際に「担当者はもう帰ってしまった」となるかもしれません。
コミュニケーション機会に関する問題を回避・軽減するには、業務内容や従業員の状況を把握しやすい仕組みを導入するとともに、下表のような取り組みを実施するとよいでしょう。
【フレックスタイム制に伴うコミュニケーション機会減少への対策】
| 社内コミュニケーション |
|
|---|---|
| 社外コミュニケーション |
|
こうした施策で対応しきれない場合、多くの人にとって出社しやすい時間帯をコアタイムに設定するなどの対策も検討しましょう。
フレックスタイム制の企業導入率と導入が多い業種・職種
自社の業務とフレックスタイム制の相性を見極めるには、「就労条件総合調査」の調査結果が役に立ちます。また、2025年3月に公開された「労働時間制度等に関する実態調査」では、産業別導入率も確認できます。
フレックスタイム制導入率、大手企業では約35%
「令和6年度就労条件総合調査」によれば、民間企業全体でのフレックスタイム制の導入率は、7.2%。企業規模によって導入率が大きく異なり、従業員数30人以上99人以下の企業では4.4%である一方、従業員数1,000人以上の大企業では34.9%でした。
全体として、企業規模が大きいほどフレックスタイム制の導入率も高い傾向が見られます。
ここ10年間の民間企業全体での推移を見ると、2015年調査では4.3%でしたが2024年には7.2%となり、2.9pt増加しました。ただ、導入率が最も高かったのは2022年の8.2%で、2023年は6.8%に下がるなど、伸び悩んでいる様子もうかがえます。
導入率が高い業種は情報通信業、低い業種は医療・福祉
2025年3月に公表された「労働時間制度等に関する実態調査」によれば、フレックスタイム制の導入率が高い上位3業種は、情報通信業、電気・ガス・熱供給・水道業、不動産業・物品賃貸業です。特に上位2業種は2割以上が導入しています。
【フレックスタイム制の導入率が高い業種】*
| 業種 | 導入率 |
|---|---|
| 情報通信業 | 24.9% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 22.2% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 11.7% |
反対に、導入率が低い業種は、医療・福祉、農業・林業、製造業でした。
【フレックスタイム制の導入率が低い業種】*
| 業種 | 導入率 |
|---|---|
| 医療、福祉 | 1.5% |
| 農業・林業 | 3.3% |
| 製造業 | 4.4% |
フレックスタイム制の導入率が低い業種は、主に対人業務が多いもの、天候などの環境に左右されやすいもの、工場など組織単位で計画的に稼働する必要があるものなどが多いようです。
*参考:「労働時間制度等に関する実態調査 第13表 産業・企業規模・事業所規模・労働組合の有無別、フレックスタイム制導入の有無、最長清算期間別事業所数・割合」(e-Stat)
フレックスタイム制を労働条件に記載している職種例
導入率の低い業種でも、フレックスタイム制を導入する方法があります。職種単位で対象者を定める方法です。
例えば、製造業でもバックオフィス系の業務なら、従業員それぞれの都合に合わせて業務を進めても大きな支障は生じません。研究・商品開発系の部署も、比較的導入しやすいでしょう。
実際に様々な企業の求人情報を見ると、以下のような職種でフレックスタイム制の従業員を募集しているようです。
【フレックスタイム制が適用されている職種の例】
| 職種 | 具体例 |
|---|---|
| IT系の職種 | ITエンジニア、Webデザイナー、動画制作・編集、EC運営スタッフ、SNS運用など |
| 事務・営業・広報 | バックオフィス業務、社内翻訳、企画、営業、営業事務、マーケティング、デザイナー、広報など |
| 研究・商品開発 | 大学や研究機関での研究、一般企業での商品開発、データ分析など |
| 建設・不動産系の職種 | 設計、CADオペレーター、インテリアデザイナー、不動産管理など |
| 製造系の職種 | 品質管理、知的財産管理、安全管理など |
| その他の職種 | キャリアアドバイザー、コンサルタント、士業 |
フレックスタイム制の導入率が低い業種では、同業他社の施策も参考にしてみましょう。
フレックスタイム制導入に必要な労使協定・36協定・就業規則と届出義務
では、フレックスタイム制の導入で満たすべき、2つの要件を詳しく見ていきましょう。労使協定や就業規則で定めるべき項目を解説します。
労使協定で定めるべき事項
労使協定においては、フレックスタイム制の基本的枠組みを定めます。会社側(使用者)から一方的に伝えるのではなく、従業員側(労働組合や過半数代表者)と十分に話し合い、双方が納得できるルールとすることが大切です。
労使協定で具体的に定めるべき項目は、6つあります。そのうち4つは必須事項であり、2つは任意です。
【フレックスタイム制導入の労使協定で定める事項】
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 対象となる労働者の範囲 |
|
| 清算期間 |
|
| 清算期間における総労働時間 |
|
| 標準となる1日の労働時間 |
|
| コアタイム(任意) |
|
| フレキシブルタイム(任意) |
|
「対象となる労働者の範囲」は、従業員個人を示して「Aさん、Bさん、Cさんに適用する」とすることもできますし、「労務部に適用する」のような部署単位とすることもできます。業務の性質と従業員の要望を考慮しながら決めましょう。
清算期間は、これまで見てきた通り、1カ月を超えるか否かで労務管理のルールが変わります。残業時間などを把握しやすいのは、清算期間1カ月以内とする方法。1カ月を超える清算期間を設定する場合は、1カ月ごとに残業時間の有無の確認が必要です。
参考:「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(2023年2月版)」(厚生労働省)pp.4-9
労使協定・36協定の届出が必要なケース
清算期間が1カ月を超えるフレックスタイム制では、労使協定の届出が義務づけられています。
また、残業や休日労働が発生する場合、事前に36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)も締結し、労働基準監督署に届出なければなりません。
【労使協定・36協定の届出義務】
- 労使協定の届出義務:清算期間が1カ月を超える場合
- 36協定の届出義務:残業・休日労働が発生する場合
これらを怠ると、以下の法律に違反してしまいます。
【労使協定の締結・届出を行わなかった場合に違反する法律】
- 労働基準法32条の3第4項:清算期間が1カ月超のフレックスタイム制では、労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る
【36協定の締結・届出を行わずに残業・休日労働させた場合に違反する法律】
- 労働基準法32条:法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲内で労働させる
- 労働基準法35条:法定休日(週に1日または4週に4日)を与える
届出を怠った場合は罰金30万円(労働基準法120条1号)、36協定なしで残業・休日労働があった場合は、6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される恐れがあります(労働基準法119条1号)。
なお、36協定を締結していたとしても、届出を行わなければ、その36協定は無効です。つまり、“36協定なし”と同じ状態になってしまいます。届出を忘れないよう、計画的に進めましょう。
労使協定の具体的な記載例や労使協定届の記入例は、厚生労働省による資料が参考になります。
参考:「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(2023年2月版)」(厚生労働省)pp.11-12、pp.19-20
36協定全般に関する解説は、以下の関連コラムもご覧ください。
コラム「36協定をわかりやすく解説!残業上限と2024年問題、届け出方法」はこちら
就業規則で定めるべき項目
労使協定で合意した内容は、就業規則にも追加してください。具体的な記載例として厚生労働省があげた項目には、以下の6項目があります。
【フレックスタイム制に関する就業規則の記載項目例】
- 適用労働者の範囲
- 始業時刻・終業時刻を従業員の決定に委ねる旨の記載
- 清算期間と総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム・フレキシブルタイムを設ける場合は、それぞれの開始時刻・終了時刻
- 「前条に掲げる事項以外については、労使で協議する」などの記載
就業規則の作成・届出義務があるのは、常時10人以上の従業員がいる事業場です。フレックスタイム制の導入に当たって就業規則を変更した場合は、「就業規則(変更)届」を作成し、労働組合または従業員過半数の代表者の意見書を添えて、労働基準監督署に届け出てください。
フレックスタイム制導入の流れとポイント
最後に、フレックスタイム制の導入の流れとポイントを簡単に解説します。円滑な導入に向けて準備を進めましょう。
(1)フレックスタイム制の導入目的と導入計画を明確にする
フレックスタイム制の導入に向けて最初に行うのは、導入目的の明確化です。自社にとってどのようなメリットがあり、どのようなデメリットが考えられるかを検討するためにも、「なぜフレックスタイム制を導入するのか」をしっかり確認しましょう。
デメリットに関しては、複雑化する勤怠管理への抵抗感が現場から出る可能性があります。その抵抗感を管理システムの導入によって軽減できないか、労務管理の負担を考慮しても重視すべきメリットがあるかどうかなどを検討することが大切です。
また、フレックスタイム制との相性は、業種だけでなく職種によっても異なります。デスクワーク中心の部署や顧客とのやり取りが少ない職種などから、実験的に導入する形でもよいでしょう。
目的と大きな方向性が明確になったら、労使協定に必要な項目の話し合いを丁寧に進めます。現場が混乱しないよう、フレックスタイム制の導入計画も策定しましょう。
(2)労使協定の締結、就業規則の変更、届出を行う
会社側と従業員側で具体的な対象者や実施方法を決定したら、次は労使協定の締結と就業規則の変更です。
一定の条件に当てはまる場合は労使協定や36協定、就業規則に関する労働基準監督署への届出が必要です。改めて下表にまとめていますので、ご確認ください。
【労使協定・36協定・就業規則の届出義務が生じる条件】
| 労使協定 | 清算期間が1カ月超であるフレックスタイム制を導入する |
|---|---|
| 36協定 | 残業時間や休日労働が発生する |
| 就業規則 | 常時10人以上の従業員を雇用する事業場である |
従業規則への記載事項と労使協定の内容は連動しますので、締結・作成を並行して進めるとよいでしょう。
(3)従業員に周知・説明を行い、研修などを実施する
以上の準備が整えば、いよいよ社内でフレックスタイム制の導入が可能です。運用開始に当たり、従業員に制度の周知を行いましょう。
【従業員に伝える内容の例】
- フレックスタイム制の導入目的
- フレックスタイム制に関する労使協定と就業規則の内容
- 労働時間の管理方法の変更と注意点
- 時間外労働や休日労働の取扱い
- コミュニケーション面でのデメリットと対策
フレックスタイム制は、適切に運用できれば業務効率化につながります。デメリットを放置して業務に支障が出ないよう、定期的にヒアリングや改善策の実施、研修なども行ってください。
フレックスタイム制の導入は労務ノウハウとタイムマネジメント力の強化から
フレックスタイム制は、従業員の柔軟かつ主体的な働き方を実現する重要な選択肢。優秀な人材の採用・確保につなげるためにも、ぜひ導入を検討したいところです。
とはいえ、労働時間の管理面で問題も起こり得ます。適切に運用するには、正しい労務管理のノウハウと一人ひとりのタイムマネジメント力が欠かせません。
多数の企業でビジネスパーソンのスキルアップをご支援してきたALL DIFFERENTでは、人事担当者や管理職の労務管理スキルの習得・向上、新入社員も含むビジネスパーソンのタイムマネジメント力向上に役立つ研修を多数ご提供しています。効果的なフレックスタイム制の活用に、ぜひお役立てください。